
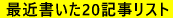
槍飛橋(やりとびばし)|高千穂峡
▶ in 高千穂峡 posted 2013.07.01 Monday / 12:05
槍飛(やりとび)
ここは、高千穂峡(五ヶ瀬川)の中で最も川幅の狭いところです。天正19年(1591年)高千穂・三田井家が県の領主(現在の延岡)高橋元種に三田井城を攻められ、落城、城を脱出した三田井家の家来達はここまで逃げのびて来ました。橋がないので槍の柄(やりのえ)を突いて渡ったという。
「手前の岩に槍を突(つ)いた者は無事飛び渡ることが出来たが、向こう側に突いた者は川の中に転落した」と伝えられており、ここを「槍飛び」と言うようになったとの事です。

槍飛橋
「槍飛」は、現在、高千穂峡の遊歩道沿いにあり、橋(槍飛び橋)がかけられております。ご覧のように川幅がかなり狭い為、大水の祭には、かなり水位が上がるらしく、橋の上にまで水が来る事もあるようで、槍飛び橋の手すりが濁流で破壊されたのでしょうか、以前行きました際には橋に仮設の鉄パイプの手すりが設けられていたこともありました。(上写真参照)
この付近の遊歩道は、大雨警報が出るような大雨の際には、通行止になることもあります。
→ 2011年 2012年の記事を参照願います。

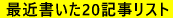
ヘルメット地蔵 (上岩戸)
▶ in 高千穂結構コアな話題? posted 2013.06.28 Friday / 07:26
高千穂町中心部より、県道7号線で、先日書いた、岩戸日向(ひなた)地区の鉾神社へ行く途中に、ヘルメットを被ったお地蔵さんがありますので、ご紹介。

「笠地蔵」はおなじみですが、これは「ヘルメット地蔵」です。
周辺を見ると、落石と思しき石が結構あるようです、どなたかが、お地蔵さんに被せたのかも知れませんね。
「上岩戸あさぎり協議会サイト」によると、“近くで落石があった際、このお地蔵さんは無傷だったとの逸話が残っています。”とありました。
いつごろからヘルメットを被っているのでしょう?
インターネット検索で少し探してみましたが、わかりませんでした。
ある方のブログの記事では、少なくとも10年以上前?から被っているようで、時々ヘルメットも新しいものに更新されるようなことを書かれてらっしゃいました。

「笠地蔵」はおなじみですが、これは「ヘルメット地蔵」です。
周辺を見ると、落石と思しき石が結構あるようです、どなたかが、お地蔵さんに被せたのかも知れませんね。
「上岩戸あさぎり協議会サイト」によると、“近くで落石があった際、このお地蔵さんは無傷だったとの逸話が残っています。”とありました。
いつごろからヘルメットを被っているのでしょう?
インターネット検索で少し探してみましたが、わかりませんでした。
ある方のブログの記事では、少なくとも10年以上前?から被っているようで、時々ヘルメットも新しいものに更新されるようなことを書かれてらっしゃいました。

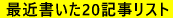
二ツ嶽神社(ふたつだけじんじゃ)
▶ in 神社写訪 posted 2013.06.27 Thursday / 08:01
鎮座地 宮崎県高千穂町岩戸215 (日出地区)
地図 MAP FAN
緯度経度(日本地理系)N=32.44.39.5 E=131.22.45.8付近です。
※ 周辺道路は狭いので運転にはお気をつけください。
御祭神 八幡神・若宮大神・菅原道真公
例大祭 10月2日
八幡神は武家の守護神ですが、鍛冶や農業の神ともいわれています。
若宮大神は家内安全の神様とされています。
建立年は不明。豊永4年(1707)の刻印のある神鏡が伝わっています。また、高千穂に八幡牡を最初に勧請した神社といわれています。

地図 MAP FAN
緯度経度(日本地理系)N=32.44.39.5 E=131.22.45.8付近です。
※ 周辺道路は狭いので運転にはお気をつけください。
御祭神 八幡神・若宮大神・菅原道真公
例大祭 10月2日
八幡神は武家の守護神ですが、鍛冶や農業の神ともいわれています。
若宮大神は家内安全の神様とされています。
建立年は不明。豊永4年(1707)の刻印のある神鏡が伝わっています。また、高千穂に八幡牡を最初に勧請した神社といわれています。
