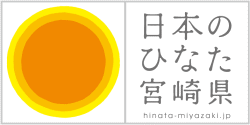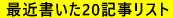
平成29年度 高千穂の夜神楽 11月18日より2月10日まで奉納
▶ in 神楽・伝統芸能 posted 2017.10.25 Wednesday / 07:26
「高千穂の夜神楽」(国重要無形民俗文化財)が、今年も11月18日(土)より来年2月10日まで、週末を中心に高千穂町内の集落で奉納されます。

平成29年度高千穂の夜神楽日程表
平成29年11月18日〜平成30年2月10日
日付 / 地区(神社) / 公民館(小組) / 神楽宿
- 11.18(土)押方(中畑) 五ヶ村西(大内東・大内西) 五ヶ村西活性化センター
- 11.18(土)岩戸(天岩戸) 下永の内(岩神東) 下永の内公民館
- 11.22(水)上野(上野) 上野(板鶴・仲町) 上野小学校跡体育館
- 11.22(水)上野(柚木野) 下組(笛原) 佐藤 和男 様宅
- 11.22(水)下野(下野八幡) 下野東(広木野) 下野東公民館
- 11.24(金)上野(黒口) 黒口 黒口公民館
- 11.25(土)岩戸(御霊) 上永の内(河地・布城) 木下 峰貴 様宅
- 11.25(土)向山(秋元) 秋元 飯干 隆 様宅
- 12.2(土)三田井(逢初天神) 下川登 下川登公民館
- 12.2(土)押方(二上) 跡取川(奥畑) 跡取川公民館
- 12.2(土)岩戸(歳) 五ヶ村(日陰) 神楽の館
- 12.9(土)押方(嶽宮) 下押方 下押方公民館
- 12.9(土)岩戸(石神) 野方野(尾の上・下角) 野方野公民館
- 12.16(土)三田井(磐下大権現) 浅ヶ部(猿伏) 浅ヶ部集落センター
- 1.13(土)河内(熊野鳴瀧) 奥鶴 奥鶴公民館(亀鶴館)
- 1.20(土)田原(広福) 下田原 下田原公民館
- 1.20(土)向山(山中) 尾狩 甲斐 勲 様宅
- 1.27(土)向山(柘ノ滝) 黒仁田 黒仁田活性化センター
- 2.10(土)田原(熊野) 上田原(今狩) 上田原公民館(なごみの館)

神楽宿への「御神前」の目安
高千穂神社で毎夜行われる、高千穂観光神楽のような、入場料のある観光向けの神楽では特に必要ありませんが、高千穂に限らず夜神楽の見学は一夜の氏子として供物を持参、奉納するのが慣例です。通常は神楽宿(神楽の開催されるところを神楽宿と呼びます。)に「受付」がありますので、初穂料(御初穂)として3千円、または、地元の焼酎2,3本の寸志(御神前)を目安に、神楽宿へ納めます。
これは、神社でのお賽銭と同じ意味合い+ほしゃどん(神楽を舞う方)や神楽宿への方への感謝の気持ちであり、「ふるまい」の食事代やお酒の対価という意味合いのものではありません。
その他、夜神楽見学の際の留意事項
最近は、公民館のようなところで奉納される集落が増えてきておりますが、民家の神楽宿の多くは窓は開けっ放しです。屋根の下というだけで、外気温とほとんど変わりません。かなり冷え込みますので、ひざ掛けや、ホッカイロなど、防寒対策を万全に!!!地区によっては、神楽宿まで車のすれ違いも苦労するような狭い道があります。
街灯はほぼ無く、道は真っ暗ですので、暗くなってからの移動は十分ご注意ください。
1・2月などは、特に寒く、夜中頃よりフロントガラスはガチガチに霜で凍りつくこともありますで、車にはスクレイパー(こさいで霜を落とす道具)を積んでおいいた方が良いです。
地区によって三脚(一脚)によるビデオやカメラ撮影を禁止しているところもあるようです。ビデオやカメラの撮影は、見学の方の妨げにならないよう高さ、場所なを選ぶなど、気を使ってください。
禁止されてなくとも、三脚の設置や・フラッシュの使用はひかえた方が良いです。
「神楽見学のマナー」ストロボは控える に同感
みやざきの神楽ガイド / みやざきの神楽魅力発信委員会編 において、神楽見学のマナーの項目の、「カメラ・ビデオの撮影」についての項目で、ストロボ(フラッシュ・スピードライト撮影)について記載があったのでに引用します。文:田尻 隆介さん(高千穂町文化財保存調査員、中央公民館長)
三脚を使用しない撮影は、特に規制はないようであるが、神事芸能であり、ストロボ撮影は舞に支障をきたすこともあるので、控えるべきであろう。/引用おわり
夜神楽でのフラッシュの発光は、場の雰囲気を乱しますし、他の見学者にとって、迷惑な行為だと思います。
神楽好き・写真を撮る者として、近年、そんなことを感じており、自分への戒めの意味もこめ、一部引用させていただきました。
夜、おなかが空いた時、何か食べるものを持参しておいた方が良いです。
あくまで、神楽は集落の方達の神事、そこに参加させて頂く、というスタンスです。

夜神楽の奉納は、秋の実りに対する感謝と翌年の豊穣を祈願するものです。
夜神楽三十三番
※神楽の番付・順序は、地域によって変わる場合があります。
- 彦舞 (ひこまい)
猿田彦命 (さるたひこのみこと)
一斗枡にのぼり四方拝する。七番までをよど七番といい、普通にはこの七番で願、成就とする。
- 太殿 (たいどの)
句句廼智命 (くぐのちのみこと)(木)・軻遇突智命 (かぐつちのみこと)(火)・金山彦命 (かなやまひこのみこと)(金)・罔象女命 (みつほのめのみこと)
天孫降臨のとき、注連を張って高天原と定め、ここに八百万神を招く舞。
- 神降 (かみおろし)
神漏伎命 (かむろぎのみこと)・おんしおの命・天忍穂耳命 (あめのおしほみみのみこと)
降神の舞で神を招く。以下三番を式三番といい、一番重要で祭典では必ず舞う。
- 鎮守 (ちんじゅ)
大屋津姫命 (おおやつひめのみこと)・柧津姫命 (つまづひめのみこと)
土地を祓い固め、神を鎮めまつる。
- 杉登 (すぎのぼり)
椎根津彦 (しいねつひこ)・莵狭津彦 (うさつひこ)・入鬼神−武甕槌神 (たけみかづちのかみ)
昇神の舞。神を送る。
- 地固 (ぢがため)
道のたんの命・事代主神 (ことしろぬしのかみ)・五十猛命 (いそたけるのみこと)・玉屋命 (たまのやのみこと)
剣、即ち水の徳で耕地を潤して国造りをする。宝渡しは護符の剣を氏子代表又は宿主に渡す式。
- 幣神添 (ひかんぜ)
彦狭知神 (ひこさちのかみ)・天日命 (あめのひのみこと)
幣による祓いの舞、願神楽。折敷に神歌あり。
- 武智 (ぶち)
弟橘姫 (おとたちばなひめ)・衣通姫 (そとおりひめ)
むちかむしとも言う。戦い準備の舞。
- 太刀神添 (たちかんぜ)
大屋津姫命 (おおやつひめのみこと)・柧津姫命 (つまづひめのみこと)
太刀の神威により厄難を払う舞。ハレワイサのサアという舞手の掛け声が入る。岩潜りと共に神添の本体、全国に見られる。
- 弓正護 (ゆみしょうご)
月夜見命 (つきよみのみこと)・天日鷲命 (あまのひわしのみこと)・経津主神 (ふつぬしのかみ)・武甕槌神 (たけみかづちのかみ)
弓を持ち悪魔を払う舞。宝渡しは弓矢を氏子(村人)に渡す式。
- 沖逢 (おきへ)
天村雲命 (あまのむらくものみこと)・思兼神 (おもいかねのかみ)・事代主神 (たおきはおいのみこと)・天穂日命 (あまのほひのみこと)
水神を祭る火伏せの神楽。天真名井の水を下すという。吹けば行く吹かねば行かぬの歌が入る。
- 岩潜 (いわくぐり)
武甕槌神 (たけみかづちのかみ)・天目一箇命 (あまのまひとつのみこと)・手置帆負命 (たおきほおいのみこと)・猿田彦命 (さるたひこのみこと)
剣の舞、白刃を持ち回転などする。安産を祈る女子が帯をたすきにしてもらう。
- 地割 (ぢわり)
荒神−素戔鳴命 (すさのおのみこと)・神主−天児屋命 (あまのこやねのみこと)・幣挿−太玉命 (ふとだまのみこと)
弓舞−月夜見命 (つくよみのみこと) ・太刀舞−武甕槌神 (たけみかづちのかみ)
かまど祭で重要な舞。屋敷祭をする。神主と問答あり。
- 山森 (やまもり)
青龍王命 (しょうりゅうおうのみこと)・赤龍王命 (しゃくりゅうおうのみこと)・白龍王命 (びゃくりゅうおうのみこと)
黒龍王命 (こくりゅうおうのみこと)・山の神−黄龍王命 (おうりゅうおうのみこと)
最も素朴な舞。山の神と二頭の獅子が出る。この後、獅子は門付に出て戸毎を祝福する。
- 袖花 (そでばな)
天鈿女命 (あめのうずめのみこと)・柧津姫命 (つまずひめのみこと)・石凝姥命 (いしこりどめのみこと)・木花開耶姫 (このはなさくやひめ)
鈿女命が天照大神のお使いにて猿田彦神をお迎えに行かれる舞。
- 本花 (ほんばな)
天鈿女命 (あめのうずめのみこと)・柧津姫命 (つまずひめのみこと)・石凝姥命 (いしこりどめのみこと)・木花開耶姫 (このはなさくやひめ)
- 五穀 (ごこく)
倉稲魂命 (うがのみたまのみこと)・保食神 (うけもちのかみ)・大田命 (おおたのみこと)・大己貴命 (おおあなむちみこと)・大宮売命 (おおみやのめのみこと)
穀種を祭る。各々膳に穀をのせ持って舞う。後之をまいて村人が拾い帰る。
- 七貴神 (しちきじん)
大国主命 (おおくにぬしのみこと) ・御子神 7人
- 八つ鉢 (やつばち)
少彦名命 (すくなひこなのみこと)
八揆とも書く。少彦名命が太鼓に乗って身軽な舞をする。
- 御神体 (ごしんたい)
伊奘諾尊 (いざなぎのみこと)・伊奘再尊 (いざなみのみこと)
酒こしの舞という。酒をつくる様によせてかまけわざをし、見物人の中にも入ってくる。
- 住吉 (すみよし)住吉神・八幡神・春日神・白鬚神
海神の舞。稲荷神楽ともいう。最初から歌が入る。
- 伊勢神楽 (いせかぐら)
天児屋命 (あまのこやねのみこと)
七段しばりの大幣を持ち舞う。岩戸を探る舞で岩戸開きの準備である。
- 柴引 (しばひき)
天香語山命 (あまのかごやまのみこと)
天香具山の柴を引き岩戸の前に飾る。これから岩戸五番、伊勢神楽と日前又は大神を加え岩戸七番という。
- 手力雄 (たぢからお)
手力雄命 (たぢからおのみこと)
天照大神が隠れている天岩戸を探し当てるところ。鈿女と入れ替わる。
- 鈿女 (うずめ)
天鈿女命 (あめのうずめのみこと)
天岩戸の前の舞。神楽の起源といわれる。
- 戸取 (ととり)
戸取明神 (ととりみょうじん)[手力雄命(たじからおのみこと)]
天岩戸を開き、天照大神に再び出て頂く。これで又世の中が明るくなった。
- 舞開 (まいひらき)
手力雄命 (たぢからおのみこと)
ついに天岩戸を開き天照大神に出て頂いたので鏡を両手に持って喜び祝い舞う。
- 日の前 (ひのまえ)
天児屋命 (あまのこやねのみこと)・猿田彦命 (さるたひこのみこと)・思兼命 (おもいかねのみこと)・天鈿女命 (あめのうずめのみこと)
外注連を祭り、天照大神の出御を祝福する。神送りの舞。麻のついた大幣をもつ。高千穂神楽特有の舞。
- 大神 (だいじん)
矢房八郎拝鷹天神 (やふさのはちろうはいたかてんじん)・道のたんの命・伊勢命 (いせのみこと)
大わだつみの神(海の幸)の清めの舞。願掛け、願ほどきの神楽。
- 御柴 (おんしば)
瓊瓊杵命 (ににぎのみこと)・天村雲命 (あまのむらくものみこと)・神主−天穂日命 (あまのほひのみこと)
(一般には十社大明神と所の氏神という)
神人一体の古風を最もよく象徴する。二神柴に乗り村人多数に担がれて外注
- 注連口 (しめぐち)
手力雄命 (たぢからおのみこと)
神送りをするところ。四人はみどりの糸をとって注連の前で舞う。舞いおろす中のヤ、正面舞い下ろすヤ、今は正面おさめましますの歌あり。
- 繰下し (くりおろし)
天児屋命 (あまのこやねのみこと)・天日鷲命 (あまのひわしのみこと)・天村雲命 (あまのむらくものみこと)・天帆負命 (あまのほおいののみこと)
雲下ろしの用意。雲綱をとり外注連に向かって舞う。
- 雲下し (くもおろし)
神漏美命 (かむろみのみこと)・手置帆負命 (たおきほおいのみこと)・天児屋命 (あまのこやねのみこと)・思兼命 (おもいかねのみこと)
太玉命 (ふとたまのみこと)(あるいは八百万神ともいう)
雲を下ろす舞。紙吹雪が舞い散ってみごとな三十三番の大成就。

〜 御神体 〜
高千穂の夜神楽関連の催し
天岩戸夜神楽33番大公開まつり
日時 11月3日(金・祝)午前10時〜午後10時場所 天岩戸神社 西本宮、斎館
神話の高千穂夜神楽まつり
11月22日(水)午後6時〜午後11時11月23日(木・祝)午前10時〜午後11時
場所 高千穂神社 神楽殿
関連ページ リンク等
平成29年度、高千穂の夜神楽の日程・場所など、詳細は下記、高千穂町資料を参照願います。➡ 平成29年度 高千穂の夜神楽日程表(PDF)高千穂町
当サイト内関連ページ
➡ 高千穂神楽
➡ 高千穂の夜神楽(上田原神楽)
➡ 宮崎の神楽

「高千穂観光ブログ」について
※本サイト内ページの内容については、その完全さに関して、いかなる保証をするものではありません。
サイト内ページに関するいかなる間違い、不掲載についても一切の責任を負うものではありません。
記載された情報・内容は、先々変更になる場合があります。
最新情報等は、公式サイト等でご確認をお願いします。
*リンクフリー*当サイト内ページへのリンクは連絡無用・Twitter、フェイスブック、ブログ、BBS等からも自由にどうぞ。
サイト内ページに関するいかなる間違い、不掲載についても一切の責任を負うものではありません。
記載された情報・内容は、先々変更になる場合があります。
最新情報等は、公式サイト等でご確認をお願いします。
*リンクフリー*当サイト内ページへのリンクは連絡無用・Twitter、フェイスブック、ブログ、BBS等からも自由にどうぞ。