

尾八重神楽(清山・地割・幣差・花鬼神・大神神楽)
- 【1Page】 尾八重神楽トップページ
- 【2Page】 清山・地割・幣差・花鬼神・大神神楽
- 【3Page】 宿神地舞・宿神
- 【4Page】 鎮守神楽・八幡・八社神楽・八子舞・稲荷鬼神
- 【5Page】 四方鬼神地舞・四方鬼神・獅子舞(荒神)・ばんぜき
- 【6Page】 神和・四人神崇・一人剱・大将軍・柴荒神
- 【7Page】 綱地舞・綱荒神・綱神楽・繰落し・衣笠荒神
- 【8Page】 伊勢神楽・手力・戸開・お清・百弐拾番・舞上
当サイトは、写真メインのサイトです。拡大写真はフルハイビジョン幅(1920pix)です。出来ればパソコン等の大きな画面でご覧ください。
主な写真は写真上をクリックすると、画面幅サイズに拡大します。拡大した画面の左上にるアイコンをクリックするとさらに拡大、マウスの回転操作でもシームレスに拡大縮小します。
スマホ等、モバイル端末などでうまく拡大しない場合には、写真下の文字リンクをタップしてください。
尾八重神楽(米良の神楽) 以外の宮崎県内で撮影した神楽の写真も、数多く掲載しております。以下をご覧ください。
➡ 宮崎県の神楽
主な写真は写真上をクリックすると、画面幅サイズに拡大します。拡大した画面の左上にるアイコンをクリックするとさらに拡大、マウスの回転操作でもシームレスに拡大縮小します。
スマホ等、モバイル端末などでうまく拡大しない場合には、写真下の文字リンクをタップしてください。
尾八重神楽(米良の神楽) 以外の宮崎県内で撮影した神楽の写真も、数多く掲載しております。以下をご覧ください。
➡ 宮崎県の神楽
〔2〕清山(きよやま)
二人舞 お神楽の始まりを告げ、お祓いをする舞(初参舞という)烏帽子に狩衣。左手に扇、右手に鈴。






〔3〕地割(じわり)
二人舞 天地を鎮め、斎場を清める舞「清山」と共に基本神楽のひとつ。
山伏特有の鎮魂動作 へんべ、尾八重特有の舞振り、カラス飛びなどの所作
に素襖 採り物=刀、榊葉、扇、鈴。








〔4〕幣差(ひさし)
二人舞 幣飾りの舞(天太玉命(あまふとだまみこと)が岩戸開きの時しめ縄を張って造らせ舞った神楽。花鬼神の地舞毛頭に素襖。後越に舞幣一対を差し、左手に扇、右手に鈴。






〔5〕花鬼神(はなきじん)
一人舞 壱岐宇多守(いきうたのかみ)(湯之片若宮大明神、尾八重神楽の祖)神面の舞年少者が舞う。神面を着け、毛頭に千早袴、後腰に舞幣二本を差す。
採り物=めん棒、扇
 令和6年の神楽は、壱岐宇多守の旧神面で舞われました。(写真5枚追加)
令和6年の神楽は、壱岐宇多守の旧神面で舞われました。(写真5枚追加)
詳細は、高見乾司氏の➡ fecebook記事(900年の時空を背負って舞う/尾八重神楽「花鬼神」)をご覧ください。










みやざきの神楽ガイド その歴史と特色(みやざきの神楽魅力発信委員会編集)
みやざきの神楽~三、県内神楽伝承の歴史(項目:小川 直之著) より一部引用
現在の宮崎県内でいつから神楽が行われたのかは、十分な資料がなく難しい課題である。
高千穂神社の文治五年(1189)の奥書をもつ 「十社大明神記」には、「七日七夜の御じんらく」とある。また、西都市尾八重には、保安二年(1121)に尾八重湯之片の集落に、湯之片神社の祖である壱岐宇多守幸延が住み着いて神楽を始めたという伝承があり、12世紀には神楽が行われていた可能性がある。
しかし、神楽催行の直接的な記録は、高千穂神社に関する長禄四年(1460)の桑之内宣命(せんみょう)(宣命は神主のこと)への文書にある「二神大明神御神楽」、同じく明応3年(1494)の十社宣命への文書にある「春秋二季彼岸神楽」などで、15世紀以降にしか出てこない。
諸塚村の日が暮神楽には天文15年(1546)の祭文資料があり、島津家の家臣で宮崎城主になった上井覚兼の日記には、天正11年(1583)6月1日に現在の宮崎市である折生迫の漁民が豊漁祈願に神楽を奉納した記載がある。
椎葉村の栂尾神楽は、栂尾神社の初代神主である黒木済門之助が元亀年間(1570~73)
に阿蘇神社から神楽を伝習したという伝承があり、古文書や記録類、伝承からは15五世紀から16世紀にかけて神楽が行われていたことは確かである。ただし、時の政権中央から離れた地方では、中世後期以前の古文書や古記録はわずかしか残っておらず、これらの記録以前には神楽がなかったと言い切れない。






〔6〕大神神楽(だいじんかぐら)
二人舞 大直日命(おおなおびのみこと)、神直日命(かむなおびのみこと)のお祝いの舞毛頭を着け素襖なし。 採り物=榊葉、扇、無幣(大神幣)各一対。






- 【1Page】 尾八重神楽トップページ
- 【2Page】 清山・地割・幣差・花鬼神・大神神楽
- 【3Page】 宿神地舞・宿神
- 【4Page】 鎮守神楽・八幡・八社神楽・八子舞・稲荷鬼神
- 【5Page】 四方鬼神地舞・四方鬼神・獅子舞(荒神)・ばんぜき
- 【6Page】 神和・四人神崇・一人剱・大将軍・柴荒神
- 【7Page】 綱地舞・綱荒神・綱神楽・繰落し・衣笠荒神
- 【8Page】 伊勢神楽・手力・戸開・お清・百弐拾番・舞上
The contents of this site are written in Japanese only Please use English translationsite. 【サイト内検索のご案内】
当サイト内には多くの神楽の関連ページ/写真があります。
以下より、当サイト内の検索が出来ます。
画像検索もできますので、写真を探すことも出来ます。
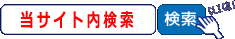
尾八重神楽(清山・地割・幣差・花鬼神・大神神楽)
Reproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.
Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.
-PhotoMiyazaki -
Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.
-PhotoMiyazaki -