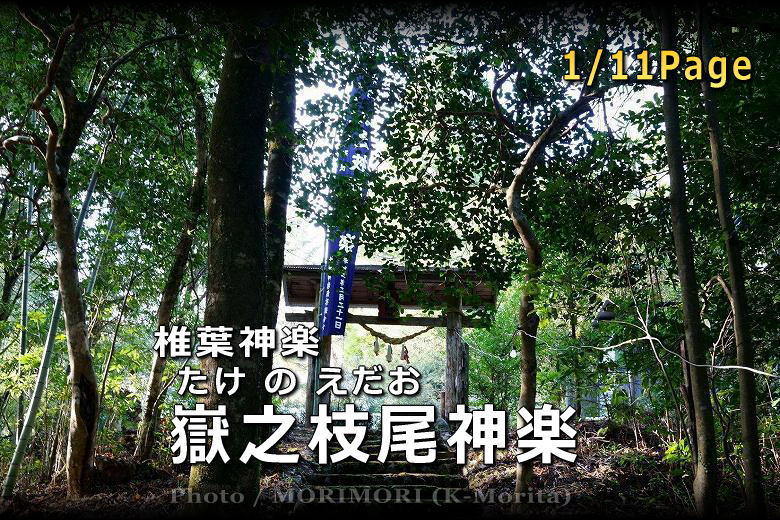
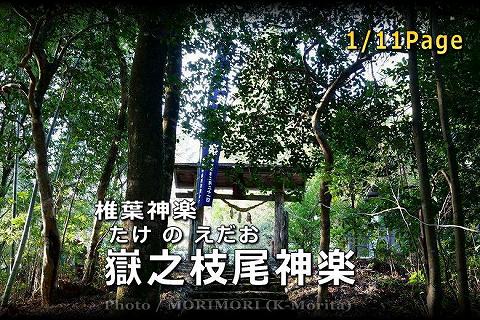
嶽之枝尾神楽(椎葉神楽) 1/11P(神事、宮神楽、大神神楽)
|【1P】神事、宮神楽、大神神楽(このページ)|【2P】注連立、注連唱行、宿借り、注連誉|【3P】注連引鬼神、御高屋誉、安永|【4P】子ども神楽|【5P】一神楽、願成就神楽、平手式三番、紋神楽|【6P】稲荷神楽、柴入神楽(★動画あり)、柴問答|【7P】大神神楽、星指、内鬼神|【8P】手力、柴引、戸取|【9P】御喜恵、牛頭天皇、伊勢神楽、岩戸舞|【10P】神粹、綱入神楽、綱問答、年ノ神、火ノ神|【11P】入増、綱切、御笠舞、神送り|嶽之枝尾神楽
嶽之枝尾神楽は、椎葉村に伝承される「椎葉神楽」(国指定重要無形民俗文化財)の中の一つです。「宿借」「注繩引鬼神」「星指」など、全国的に類を見ない演目が多く、貴重な伝承と云われる。
神楽は、全国でも珍しい八調子(普通は六調子)であること。太鼓は烈しく、舞は静かなものが多いのが特徴。神社拝殿、神前の畳の間を「御神屋」とし、さらに外庭にしつらえられた「外神屋」二か所で奉納されるのも嶽之枝尾神楽の特徴の一つとなっています。
以前は、竹ノ枝尾の日当・日添・臼杵又の三集落において、輪番制により神楽宿を定めて執行されていたようですが、昭和44年の嶽之枝尾神社改築後は、ほぼ嶽之枝尾神社で奉納されております。
近年の神楽奉納は、12月第一土曜~日曜で、午後に降神の儀を執り行い、午後5時頃より神事を行い、神楽5時半頃から宮神楽で始まります。
 【情報追記】
【情報追記】令和7年度「嶽之枝尾神楽」は中止になったようです。
平成30年度 嶽之枝尾神楽
平成30年12月1日(土)~12月2日(日)
嶽之枝尾神社
宮司:椎葉勇
保存会長:中瀬博光
神楽頭取:椎葉一 椎葉広之
主な特徴的な神楽(見どころ)の時間帯は以下
18:00 注連立
18:40 宿借
19:20 注連鬼神
02:30 星差
以下は、嶽之枝尾神楽(宮崎県教育委員会文化財課平成29年3月発行PDF)より 一部引用。
面:めしょう面、鬼神、手力、戸取 等
楽:太鼓、縦笛、横笛、楽板、鉦、法螺貝
装束:白の舞衣、袴、カラス折れ(侍烏帽子)、赤鉢巻、宝冠、箕、笠、毛笠 等
採り物:御幣、面棒、扇、鈴、弓、矢、刀、盆、榊枝、襷、小槌 等
文書:「昭和22年 嶽枝尾神社祭例格式 中瀬淳編」や昭和30年前後に記された「平田大明神 嶽之枝尾神社唱行」の写し等が保管されている
一部の演目で世襲制が残っている。保存会会員は20名、高齢化は否めないが、各々が舞、楽、唱行を覚え、誰もが出来るように練習をしている。韓国や東京での公演など、神楽継承を目的とした保存活動にも力を入れている。 / 引用おわり。
椎葉神楽 26地区
平家落人の里「椎葉村」で脈々と受け継がれてきた「椎葉神楽」。その起源は明らかではないが、神楽で歌われる「唄教」(唱え言)は室町中期以前ではないかと推測されている。狩猟や焼畑など山の生活を表現、全国的に珍しい曲目や近世以前の古い形態を今に伝えていることが特色で、その価値は芸能・歌謡・信仰史上において高く評価されています。
椎葉神楽は、現在村内26地区で伝承されていますが、それぞれに違った特徴を持っている。
◆印は、令和6年10月時点で夜神楽が予定されている地区
- 下福良地区:◆十根川、仲塔、奥村、財木、木浦、胡麻山、◆夜狩内、◆上椎葉、村椎、若宮
- 大河内地区:◆栂尾、大藪、◆大河内、◆合戦原、◆矢立、◆嶽之枝尾、◆小崎・川の口
- 不土野地区:◆尾前、◆向山日当、◆向山日添、◆尾手納、◆古枝尾、◆不土野
- 松尾地区:栗の尾、畑、水越
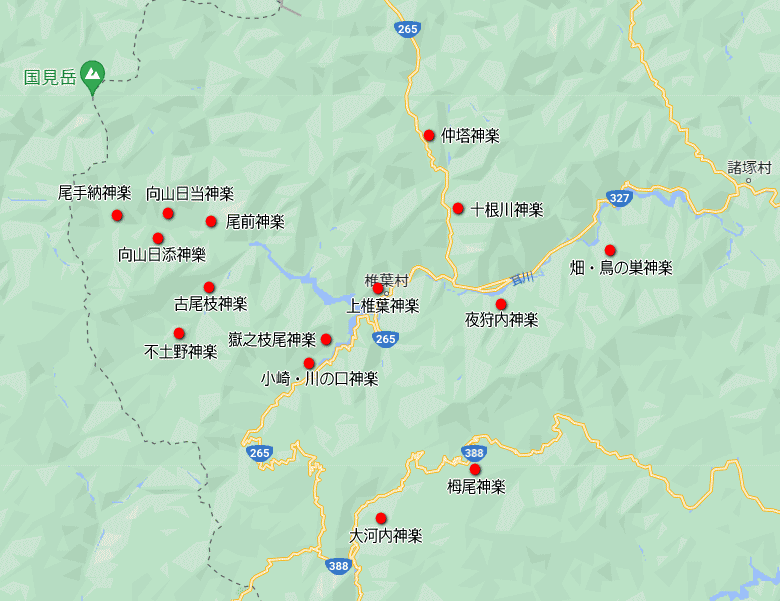
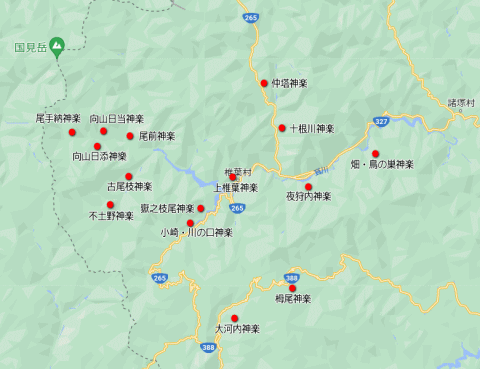
GoogleMapをベースに、過去の夜神楽開催位置を記載
令和7年 椎葉神楽日程表(2025年10月23日+追記あり)
| 月 | 日 | 神楽名 | 神楽宿 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 22日 - 23日 | 栂尾神楽 | 栂尾神社拝殿 | 18時 - 翌10時(夜神楽) | |
| 29日 | 合戦原神楽 | 合戦原王宮神社 | 19時 - 23時(半夜神楽) | ||
| 29日 - 30日 | 小崎・川の口神楽 | 小崎神社 | 17時 - 翌3時(夜神楽) | ||
| 尾手納神楽 | 尾手納公民館 | 19時 - 翌9時(夜神楽) | |||
| 12月 | 6日 | 矢立神楽 | 矢立集会センター | 15時 - 22時(半夜神楽) | |
| 6日 - 7日 | 向山日添神楽 | 峰越の館(向山日添公民館) | 19時 - 翌9時(夜神楽) | ||
| 嶽之枝尾神楽(中止) | 嶽之枝尾神社 | 17時 - 翌4時(夜神楽) | |||
| 不土野神楽 | 不土野生活活性化センター | 19時 - 翌7時(夜神楽) | |||
| 13日 - 14日 | 大河内神楽 | 大河内八幡神社 | 19時 - 翌9時(夜神楽) | ||
| 上椎葉神楽 | 椎葉村開発センター | 18時 - 翌9時(夜神楽) | |||
| 尾前神楽 | 尾向交流拠点施設イロリ | 19時 - 翌9時(夜神楽) | |||
| 古枝尾神楽 | 古枝尾センター | 15時 - 翌4時(夜神楽) | |||
| 20日 | 大藪神楽 | 大藪集会センター | 17時 - 21時(半夜神楽) | ||
| 20日 - 21日 | 十根川神楽 | 十根川神社 | 19時 - 翌10時(夜神楽) | ||
| 向山日当神楽 | 郷の家(向山日当公民館) | 19時 - 翌7時(夜神楽) | |||
| 夜狩内神楽 | 夜狩内集会センター | 19時 - 翌4時(夜神楽) | |||
| 中止 | 栗の尾神楽(神事のみ) 水越神楽(神事のみ) 畑・鳥の巣神楽(神事のみ) 仲塔神楽(神事のみ) 財木神楽 村椎神楽 奥村神楽 木浦神楽 胡麻山神楽 若宮神楽 | ||||
かならず直前情報の再確認を
椎葉神楽は集落の「しきたり」により、直前でも中止になる事があります。
お出かけの際には直前まで、椎葉村観光協会サイトのお知らせで最新情報の再確認をお願いします。
嶽之枝尾神楽(椎葉神楽) アクセス・地図等の情報
嶽之枝尾神社(近年はほぼ嶽之枝尾神社で奉納されておりますが、民家で行う事もあります。椎葉村観光協会サイトなどでその年に再確認をお願いします。)
住所:〒883-1602 宮崎県東臼杵郡椎葉村大河内1949
以下の地図は、神社への登り口のおおよその場所です。
神社へ登る道路(距離100m程)は、神楽当日、一般車両進入禁止となっていると思いますので、入口周辺(付近に何ヶ所か駐車スペースあり)に車を駐車の上、坂道を徒歩で向かいます。
地図:GoogleMap Mapfan Mapion
緯度経度:32度26分18.16秒 131度7分47.34秒(日本地理系)
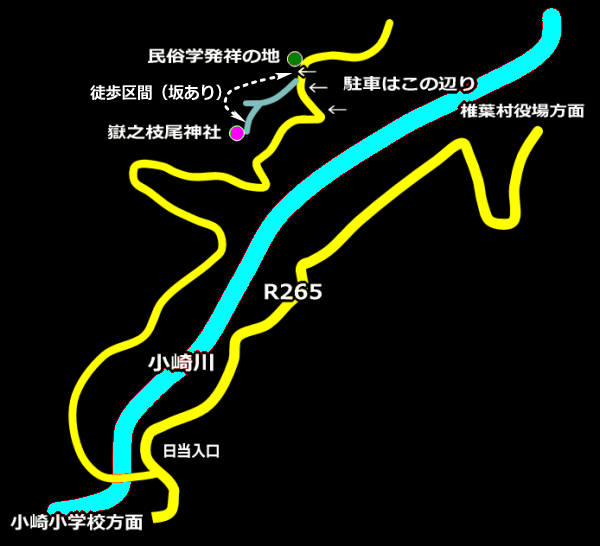
嶽之枝尾神社周辺の概略地図です。
西都市~西米良方面からも北上アクセス出来ますが、災害等で通行止区間がありますので、確認をお願いします。
通れても、道路は狭く、車がすれ違い出来ない区間も多いので、運転に疲れると思います。
折角の夜神楽見学、運転に疲れ、到着した頃はグッタリでは困ります。車の車幅感覚や、運転に不慣れな方にはに西米良方面からのアクセスは避けた方が良いかと思います。
はじめて行く、夜神楽は、明るい内の移動をおすすめします。
当サイトは、写真メインのサイトです。拡大写真は1920pix幅です。出来ればパソコン等の大きな画面でご覧ください。
主な写真は写真上をクリックすると、画面幅サイズに拡大します。拡大した画面の左上にるアイコンをクリックするとさらに拡大、マウスの回転操作でもシームレスに拡大縮小します。
スマホ等、モバイル端末などでうまく拡大しない場合には、各写真下に記載した文字リンクをタップしてください。
当サイトでは、嶽之枝尾神楽(椎葉神楽) 以外の宮崎県内で撮影した神楽の写真も、数多く掲載しております。以下をご覧ください。
➡ 宮崎県の神楽
竹の枝尾日当集落にて奉納
嶽之枝尾神楽は、椎葉村南部を流れる小崎川流域に位置する竹の枝尾日当集落にて奉納される。今回、神楽が奉納された「嶽之枝尾神社」は、写真正面左の大きな杉木立がある付近です。


嶽之枝尾神社
嶽之枝尾神社は、小崎川左岸に鎮座する竹の枝尾日当に鎮座。創建は不詳であるが、元久二年(1205)の勧請と伝え、往古より平田大明神と称し、地内日当、日添、臼杵又の氏神として崇敬されてきた。明治四年嶽枝尾神社と改称し、同七年十二月村社に列せられた。


「御神屋」と「外神屋」の様子
神前 畳の間を「御神屋」とし、外庭に「外神屋」をしつらえ、一番の宮神楽から三十三番の神送りまで夜通し神楽が奉納されます。見学の席について(平成30年の例)
「御神屋」の席は、神前に向かって右側が、奉仕者・祝子、地元の方、関係者などが座り、外部からの見学者は主に左側に座りました。
太鼓の後ろ側(写真手前)周辺でも見学可能ですが、前半の「外神屋」と行き交う番付や、稲荷神楽、柴入神楽、柴問答、神粹、綱入神楽、綱問答などの際には、一度席を空ける必要がありますので、この周辺には座らない方が、落ち着いて神楽を見学できるかと思われます。
室内とは言え、12月、窓は開けっ放しですので、防寒対策は万全に。




「御神屋」と「外神屋」 ~
(明朝の撮影)
(明朝の撮影)
祭壇の神饌
祭壇には御神饌、神楽面、猪の頭も供えられていた。


神事
神楽に先立ち「神事」が行われた。神社拝殿に設えられた「御神屋」は神社正面に祭壇(高天原)を設置、天上からは「雲」と呼ばれる天蓋がつるされ、周囲には「彫物」と呼ばれる紙が掛けられている。


平成30年度 神楽順次
- 【-】宮神楽(二人舞) 神迎えの神楽で宮もと神楽ともいう。神社で奉納する一番目の神楽である。
- 【-】大神神楽(四人舞) 官神楽ともいう。各神楽を代表するかぐらである。新入者は此の神楽から練習を始める。基本神楽である。
- 【1】注連立(全員) 注連の事を「しゆみ山」(須弥山)という。世界で一番高い山と言うことで偉大なる物を表している。
- 【2】注連唱行(一人舞) 内神屋で祓い清め、外神屋に出て、外神屋で注連の唱行をとなえる。剣の広めともいう。
- 【3】宿借り(二人舞)旅人(山の神)が神楽宿の主人と問答の末、神楽宿を借受ける。悪魔を払い、村に寿福を受ける神が出現したさまを現す。
- 【4】注連誉(二人舞) 注連祝の神楽で、内神屋、外神屋で舞う。注連祝の神楽である。
- 【5】注連引鬼神(二人舞) 二人舞で(荒神でもあり氏神でもある)内神屋で舞い、外神屋で注連を引き、八百萬代の神達を引き集める。
- 【6】御高屋誉(一人舞) 太鼓を打ちながら五方位(東・西・南・北・中中方)の唱行を唱え、又太鼓打ちの音頭に合わせ祝子と共に誉める。
- 【7】安永(四人舞)御幣の手、御盆の手がある。右手に鈴と御幣を合わせ持ち、振りながら座したまま安永の唱行を唱えると立四方舞い終わる。
- 【-】子供神楽 神粹(四人舞) 手力(一人舞)
- 【8】一神楽(二人舞)神仏混合の時代の神楽といわれ、終わりに神屋座中央に太鼓を伏せ、神官、頭取、舞子がとりかこみ、ダラノ経、五方立唱え終わる。
- 【9】願成就神楽 一年間の無病息災を祈願して、一年間が無事に終了した願成就の神楽である。大神神楽と同じである。
- 【10】平手式三番(二人舞) 前段で平手の舞、後段で刀を抜き、式三番を舞い上げる。
- 【11】紋神楽(二人舞) 狩猟と豊作を祝う神楽である。矢の手、弓の手がある。最後に盆の手、神米をまきちらして終わり。
- 【12】稲荷神楽(四人舞) 舞初めに歌と唱行あり農作物の植付から虫供養収穫まで豊作祝に稲荷大明神に奉納する格式高い神楽である。
- 【13】柴入神楽(若い祝子)稲荷神楽の後半に(稲荷山)の事、若い祝子が芝を持って神楽を舞う神屋座に入れる「ヘイトコヘイサヘイサッサ」繰り返し入れる。
- 【14】柴問答(二人舞) 神主と荒神の問答である。初め神主が荒神を罵るため荒神が荒れる。仲裁役が入り御酒が出て終わる。
- 【15】大神神楽(四人舞) 神楽宿で舞う大神神楽で前述べた通りで基本神楽で代表的ば舞いでもある。
- 【16】星指(一人舞) 風神払そして、太陽、星、お月様が唱行の中で東から出、西に沈むまで歌ってあり、星祭りの舞いである。
- 【17】内鬼神(二人舞) 二人舞いて、内神屋座だけで舞う鬼神である。(鬼神は荒神でもあり氏神でもある。)
- 【18】手力(一人舞) 天照大神が天の岩戸にお隠れになったとき箱根山に駆け登り、榊を一本根こぎにし岩戸の前に植え、曲玉や鏡を掛けた其の折の舞い。
- 【19】柴引(一人舞) 手力の舞と同じで、榊の葉を引き合って舞う。
- 【20】戸取(一人舞) 美濃の国の住神戸隠の大明神は天の岩戸の前に参り百千八萬才の力を出し天の岩戸を引き破りし時の舞い。
- 【21】御喜恵(四人舞) 季節を歌った神楽おきえーの御天で餅を搗き神様に供えることを歌って舞う。
- 【22】牛頭天皇(四人舞) 中国の祭神で中国で疫病が流行し牛頭天皇の神が疫病を祈祷により追払った舞。日本の祇園様と同じ。
- 【23】伊勢神楽(一人舞) 嶽之枝尾神楽で一番各式の高い神楽で神話と伝説の唱行と歌があり宮司の一人舞である。
- 【24】岩戸舞(二人舞) 天の岩戸より手力男命が天照大神の御手を取り迎えれし神楽で世の中が明るくなった。
- 【25】神粹(四人舞) 抜身の太刀を持、太刀揃、乱れ舞、めぐり舞、向い舞等、悪病退散の舞。朝の目覚まし神楽という。
- 【26】綱入神楽(若者・祝子) 神粹神楽のめぐり舞の時、若い祝子衆が雄綱(大蛇)を持って神屋座に入れる(柴入り神楽と同じである)
- 【27】綱問答(二人舞) 神主と荒神の問答である柴の問答と同じで仲裁役が入り御酒を出して納める。
- 【28】年ノ神(二人舞) 猿田彦命が稗と粟の穂を両手に持ち、年の祝と作祭りをコッケイに舞う神楽でトンカンコウ舞ともいう。
- 【29】火ノ神(二人舞) 火の神神楽で二人で神屋座より台所を廻りながら舞う。
- 【30】入増(四人舞) 四人で外神庭で舞う「一神楽」の上ん調の舞い方とほぼ同じで、右手鈴、左手太刀鞘のままで抜くことは無い。
- 【31】綱切(全員)【32】綱主(二人) 外神屋の前に雄綱(大蛇)宮司以下祝子が次々に太刀で綱切る「剣を賜いて綱の心は・・・・・ でんずでんずや」と歌って切る。
- 【33】御笠舞(全員) 四人舞で、他の祝子は全員拝殿の前に立ち注連を引き「ヨイヤサッサヨイヤサッサ」囃しながら注連をゆする。
- 【34】神送り(祝子全員)
神楽の写真(全11ページ 約200枚)
〔肖像権・プライバシー権について〕
神楽を舞われている方、神楽関係者、神楽への一般参加者以外の見学者については、肖像権、プライバシー権の観点より、お顔が認識出来ない程度にボカシ加工処理を行いました。
尚、地元の方のエリアについては、写真がそれ程鮮明ではないことと、記念にもなろうかとの考えの元、特に後ボカシ処理は行っておりません。
何か不都合などございましたら、メールを頂ければ、対応しますのでご連絡をお願いします。
宮神楽(二人舞)
神迎えの神楽で宮もと神楽ともいう。神社で奉納する一番目の神楽である。






大神神楽(四人舞)
官神楽ともいう。各神楽を代表するかぐらである。新入者は此の神楽から練習を始める。基本神楽である。










神楽見学のエチケット(椎葉村サイトより引用)
〔1〕神楽は、集落の神聖な祭りです。地元の祭りに参加する気持ちを持ちましょう。〔2〕椎葉村では、1人あたり、祭りに供え物(地元の焼酎2升~3升)もしくは、御祝い(3~5千円)を持っていく習わしがあります。
〔3〕ビデオや写真撮影は、他の見学される人の迷惑になることもあります。前もって保存会や神楽宿にご相談ください。
〔4〕10人以上の団体の場合は、事前に保存会に連絡し、許可を得てから見学してください。
以上
当方が考える「夜神楽見学上の留意・マナーなど」
一夜の氏子として参加させていただくというスタンスで
宮崎県内各地で奉納されている神楽は、「見世物」ではありません、地域の「祭り」「奉納」です。一夜の氏子として参加させていただくという減り下りスタンスでおねがいします。車で行かれる場合
山間部の夜神楽は、道中、道が大変狭く、対向車が来た場合、延々バックしないとすれ違い出来ないところもあります。街灯などはもちろんのこと、ガードレールも無いところも多いです。場所によっては、カーナビに道が出ないところもあります。道を尋ね様にも人家が見つからないケースも多々あります。出来れば、明るい内に現地入りして、夜が明けてからの移動をおすすめします。
12月、1月、2月の夜神楽は、朝、車の窓ガラスに霜がべったり付いていることがありますので、フロントガラスを覆うようなシートをかけて置くと良いです。また、霜落としのスクレーパーや霜取りスプレーを車に積んでおくと安心です。
1月、2月、山間部では、たまに雪が積もることもあります。特に高千穂、椎葉、諸塚の神楽へお出かけ前には、天気予報のチェック、タイヤチェーンなど滑り止めの準備を。
初穂料の奉納
夜神楽は、一夜の氏子として参加させていただくというスタンスで、供物を持参、奉納します。通常、神楽宿(夜神楽が奉納される神社など)には「受付」があるので、焼酎2升(奉納)、または現金3,000円~程度を「初穂料」として包んだものを奉納します。
焼酎などは地域で好まれる銘柄などありますので、「初穂料」の方が無難では?と、私は思います。
これは、神社でのお賽銭と同じ意味合い+奉仕者(神楽を舞う方)へや神楽宿への感謝の気持ちであり、「ふるまい」の食事代やお酒の対価ではありません。
市町村などの主催で、保存会が一堂に集まり開催される「神楽まつり」などでは、お賽銭箱が用意されていると思いますので、お賽銭を入れればよいかなーと、個人的には思います。
「子ども神楽」が奉納されるところも多くあり、「おひねり」が投げ込まれます。ご祝儀用のポチ袋などを事前に準備しておくと良いと思います。
夕食・夜食・アルコール類など
地域によっては、蕎麦、ご飯などのふるまいがあったり、折詰をお返しに頂いたり、外で婦人会などの、うどん・蕎麦などの販売があったりするところもありますが、何も無いところもあります。神楽宿(神楽の奉納場所)近くにコンビニなどはまず無いので、自身の夜食(手軽に食べられる、おにぎりなど)・飲み物などは事前に購入持参した方が良いと思います。
アルコール(宮崎は焼酎がメインです。)が振舞われることもあると思いますが、お車の方は、帰りの時間を逆算して酒気帯び運転にならぬよう適度に抑制を(^^;)
防寒には万全を期して
12月~2月の夜神楽は、とにかく寒いです。 ダウンウエア+防寒インナーなど暖かい服装で、ネッウォーマー、帽子、貼るホッカイロ装備、足元から冷えるので、靴下に貼るホッカイロも忘れずに。外で奉納される神楽でも、ムシロの上に靴を脱いで上がる場合も多いので、靴下は二重に履き、柔らかい素材の上履きみたいなものを持参しておくと良いです。座布団(クッション)、ひざ掛け毛布などもあると随分違います。
外で見る神楽は、敷物等無い場合でも対応出来るよう、折りたたみの小さ目のイスも車に積んでおくと良いです。
見学場所について
保存会や、関係者の座る場所が決まっていたり、舞い込みなどの際、邪魔になるところなどもあります。早めに行って見学場所を確保される場合、ここで見学しても大丈夫ですか?と、保存会の方などに確認した方が良いです。写真・動画などの撮影について
- 神庭には立ち入らないこと
神楽が舞われる神庭内には、絶対立ち入らないこと、神庭内に三脚の足を入れたり、バックや・カメラ・レンズなどモノを置かない事。
- フラッシュ(ストロボ/スピードライト)について
2017年4月に発刊された、みやざきの神楽ガイド / みやざきの神楽魅力発信委員会編 / 鉱脈社 という本の中の、神楽見学のマナー項目、「カメラ・ビデオの撮影」の項目で、ストロボ(フラッシュ・スピードライト撮影)について、高千穂町文化財保存調査員、中央公民館長 田尻 隆介氏は、"神事芸能であり、ストロボ撮影は舞に支障をきたすこともあるので、控えるべきであろう。"とコメントされておりました。
以前宮崎市で開催された、「みやざきの神楽シンポジュム」でも、フラッシュが及ぼす影響について、とり上げられたことがあります。
室内で舞う神楽には、ストロボが無くとも、最近の高感度性能の良いデジカメ・スマホなどでは感度を上げて撮れば問題ないとは思いますが、外に神庭を設け、星空の下、裸電球数個の下で舞われる、米良系の夜神楽などでは、正直辛いものがあります。
ただ、闇雲にストロボ乱用している方を見かけるのも事実です。ストロボの閃光は、神楽を鑑賞してる方にも迷惑だろうと思います。
周りに気配り目配り、ストロボはここぞという時だけ、最小限に留めたいものです。
- 三脚の使用
県内の神楽では三脚の使用を全面禁止しているところもあります。制限無くとも、三脚は周りの見学者にとって迷惑なので自粛した方が良いと思います。
- 神事の最中は、無暗にシャッターを切らない。
厳粛、静かな中でのシャッター音は結構耳障りなものです。
写真とは関係ありませんが、お祓いの最中は、帽子などをとるよう心掛けたいものです。
- 写り込んだ一般観客の方の肖像権・プライバシー権に配慮を
写真内に観客の方が写り込んでいる場合、SNSなどに掲載する際には、お顔が認識できない程度の画像サイズにするか、ボカシをいれた方が無難かと思います。
|【1P】神事、宮神楽、大神神楽(このページ)|【2P】注連立、注連唱行、宿借り、注連誉|【3P】注連引鬼神、御高屋誉、安永|【4P】子ども神楽|【5P】一神楽、願成就神楽、平手式三番、紋神楽|【6P】稲荷神楽、柴入神楽(★動画あり)、柴問答|【7P】大神神楽、星指、内鬼神|【8P】手力、柴引、戸取|【9P】御喜恵、牛頭天皇、伊勢神楽、岩戸舞|【10P】神粹、綱入神楽、綱問答、年ノ神、火ノ神|【11P】入増、綱切、御笠舞、神送り|
The contents of this site are written in Japanese only Please use English translationsite. 【サイト内検索のご案内】
当サイト内には多くの神楽の関連ページ/写真があります。
以下より、当サイト内の検索が出来ます。
画像検索もできますので、写真を探すことも出来ます。
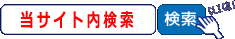
嶽之枝尾神楽(椎葉神楽) 1/11P(神事、宮神楽、大神神楽)
Reproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.
Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.
-PhotoMiyazaki -
Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.
-PhotoMiyazaki -