

「八幡様」桂正八幡神社の主祭神の舞
桂大神楽 トップページ 〔諸塚神楽〕
 国の文化審議会は令和8年(2026年)1月23日「諸塚神楽」を重要無形民俗文化財に新たに指定するよう、文部科学相に答申したようです。
国の文化審議会は令和8年(2026年)1月23日「諸塚神楽」を重要無形民俗文化財に新たに指定するよう、文部科学相に答申したようです。
令和7年10月29日(水)国立能楽堂(東京都渋谷区)で、桂神楽の公演が行われました。
観覧は無料、事前予約が必要でした。
詳細は ➡ 当サイトブログ記事をご覧ください。
このページでは、令和二年に、諸塚村諸塚神社で奉納された「桂大神楽」の写真を約250枚、18ページにわたり掲載しております。
(「杉のぼり」は4K動画、また、+番外編:スナップ写真(スライドページ)もあります。)
1920pixの拡大画像もありますので、出来ればパソコンなど大きな画面でご覧ください。
平成から令和の御代に 奉祝 大神楽奉納
日時:令和2年2月15日~16日 舞入れ:午前10時50分 神下ろし:午前12時場所:諸塚神社 神楽殿
桂神楽について
桂神楽の起源については明らかではありませんが、桂村の始まり、特に桂正八幡神社との深い関わりがあるものと考えられます。 桂正八幡神社は南北朝時代(1336~1392年)に関東かつらぎの国より勧請したと伝えられています。桂神楽は俗に「かつらぼうり」とよばれて、高千穂の荘と呼ばれた現在の西臼杵や東臼杵郡の諸塚村や椎葉村、熊本県の蘇陽町等広い地域で伝承されていたと伝えられております。
大神楽(桂神楽では夜神楽のことを言う)は、古くは戦勝祈願や武運長久の祈願(八幡神社の御祭神が応神天皇「誉田別の命」であることに由来している)で大神楽を奉納していたようで、近年では宮遷宮やお日持ちの願成就といった特別な年ににしか奉納されない夜神楽となっています。
普段は諸塚神社や矢村稲荷神社の例祭などで神楽三番が奉納され、桂正八幡神社の例祭では神楽三番と願成就神楽、旧暦初午祭には稲荷神楽が奉納されています。
平成元年一月に村指定の文化財、平成三年十一月には県の無形文化財として指定を受けました。自然の恵みと神々への感謝を表した素朴な舞いを堪能してください。
桂神楽保存会一同 (当日頂いた資料より)
「幻の神楽」大神楽(夜神楽)奉納
桂神楽は普段、諸塚神社や矢村稲荷神社の例祭などで神楽三番〔東征・杉のぼり・八幡様(座はり)〕が昼神楽として奉納されています。今回のような夜を徹して奉納する「夜神楽」は「大神楽(おおかぐら)」と称され、宮遷宮や大願成就といった特別な時に奉納されています。 不定期で奉納されるため“幻の神楽”といわれております。
近年では、平成27年に大神楽が奉納。前回から5年ぶりの大神楽奉納でした。
平成以降の「大神楽」
- 平成4年(1992年) 諸塚神社
- 平成9年(1997年) 桂正八幡神社
- 平成12年(2000年) 矢村稲荷神社
- 平成17年(2005年) 諸塚神社
- 平成23年(2011年) 諸塚神社
- 平成27年(2015年) 諸塚神社
- 令和2年(2020年) 諸塚神社
75番程を約20時間かけて舞う
宮崎県内で奉納される夜神楽は通常、夜に始まり朝までが一般的ですが、桂大神楽は番付こそ二十二番ですが、一番がその中分かれているものも少なくなく、全部合わせると七十五番程ありますので、15日午前中より16日朝まで、約20時間かけての奉納となりました。椎葉村の十根川神社、高千穂町黒仁田の神楽と同じ系統
桂神楽は他の諸塚神楽(戸下神楽、南方神楽など)とは趣を異にしていて、むしろ椎葉村の十根川神社、高千穂町黒仁田の神楽と同じ系統といわれているようです。当サイト内諸塚神楽関連ページ
➡ 諸塚神楽
➡ 戸下神楽
➡ 南川神楽
諸塚神社


本殿祭(神殿祭)
諸塚神社境内に祝子が参列、神社拝殿で神殿祭が執り行われた。新元号"令和"を奉祝しての大神楽にふさわしく、大勢の参拝者が訪れた。










神宿(立岩公民館)


全番付(各舞いの写真ページへリンクしてます。)
舞入れ
(全員) 10:50神宿よりご祭神、お供の方と共に舞い込む。


【1】宮神楽
(二人舞い) 11:05宮神楽は、神社の前や鳥居遷宮の際に舞う神楽で、東征の上のじからの立ち舞いと同じである。神前を清める。


【2】荒神の言い句
(三人舞い) 荒神一方二方、神主 11:30神主と地主荒神との問答神楽。宮清めとして行われる。桂神楽では新しく宮が建ったり、鳥居建立の折に宮神楽とともに行われる。


【3】神おろし
(全員) 12:00八百万の神々をみこうやにお迎えする神楽。
【4】とうせい(東征)
(二人舞い) 森のしょうぎょう 12:30通常、例祭等で最初に舞われる神楽。神楽の入門時に練習することで、他の神楽にも通用してくる。大神楽の時だけ森のしょうぎょうがはいる。


【5】杉のぼり
(二人舞い) 13:00桂神楽の中で特徴である「からすとび」が後半にある。早く、激しい舞いになる。


【6】おだいじん
(三人舞い) 1番~11番 13:30伊勢天正大神のいわれをとく しょうぎょう、及び神楽。


【7】たぢからさま
(二人舞い) 面と舞だし 16:30太力男命の舞い。


ぢわり
(四人舞い) 1番~13番 17:00大地の神を敬う舞い。五穀豊穣に感謝する (ちょうし、盃、しらきの豆腐)


【9】ゆみのしょうご
(二人舞い) 1番~6番 19:30弓、矢を持って舞う 狩猟の舞いとされる。
【10】八幡様
(二人舞い) 八幡様の面と舞い出し 20:50桂正八幡神社の御神体の舞。桂神楽三番として東征、杉のぼりと共に例祭の時に舞われる。


大祓
21:30夜中のみこうや清めが行われる。その後、夜中のぞうすいを食す慣わしがある。観客席にも振舞う。
【11】夜中のとうせい
(二人舞い) 22:00みこうや清めとして舞われる。


【12】しばいれ
(全員) 22:20かまど荒神が榊束にまたがり、みこうやに舞い込む。
【13】荒神の言い句
(三人舞い) 荒神一方二方、神主 22:30問答は【2】と同じである。日々かまどの火を使うことへの感謝の意がある。古くから地主荒神、かまど荒神は大事にされてきた。


【14】かんずい
(五人から一人舞い) 1番~7番 23:00かんずいは桂神楽を代表する舞いといわれ、真剣白刃による立ち舞い。ほしゃこはこの神楽が終わるまでみこうやの外に出て身を汚さずと言われている。


【15】みかさ神楽
(十人舞い) 1:00女装したほしやこが田植えの舞を行う。
【16】稲荷神楽
(二人舞い) 1番~7番 1:30稲荷大明神のしょうぎょうを説く 五穀豊穣の舞であり旧暦初午の日に舞われる。


【17】ごってんのう
(四人舞い) 1番~6番 4:20山の神の舞。
【18】おきえ
(二人舞い) 4:20水神(海)の舞。
【19】歳の神
(二人舞い) 5:40歳徳神(その年の吉方位の神・万事に吉)のしようぎょうを説く 五穀豊穣、子孫繁栄の舞であり目覚まし神楽としてこっけいな舞をする。


【20】岩戸五番の開き
しょうぎょう・伊勢神楽(一人舞い) 6:00岩戸神話のいわれをしょうぎょうで説く。
しばとり(一人舞い)
「おぼろ月夜のごとくなりたもその時、ふでんおうはしばを引きこぎ」としようぎょうに唄われるしばとりの舞。
戸とり(一人舞い)
「と隠しの明神なましまして、おくせんざいの力を出し弓手の戸を取り……」とうたわれる戸とりの舞。


【20】岩戸五番の開き
とんちく面うずめの舞とされる。
大神宮引き出し 6:40
太力男命力が天照皇大神引き出す舞。


【21】願成就神楽
(三人から一人舞い) 1番~6番 7:00祈願裁就の舞 高天の原より出た二本の綱を二人で持って舞う よじれた網が解けることにより成就を表す 神と人との心をつなぐ。
【22】神おくり
(全員) 8:00すべての神楽が終わり八百万の神々を元の社に納める舞。


桂大神楽 アクセス・地図等の情報
諸塚神社鎮座地住所:〒883-1302 宮崎県東臼杵郡諸塚村七ツ山7190
地図:GoogleMap Mapfan Mapion
緯度経度:32度35分4.01秒 131度19分27.54秒(日本測地系)
前回同様、令和2年も、すぐ近くにある「立岩小学校跡のグラウンド」が駐車場となっておりました。

駐車場の位置など概略地図

見学場所などの概略図
素晴らしい神楽でした。
「桂神楽」自体は、数番の公演(平成24年(2012年)県庁で しばとり、戸取り、大神宮引き出し、 先日、2020年神楽シンポジウム(メディキット県民文化センター)で 荒神の言い句、みかさ神楽)を見学したことがありますが、現地では今回初めての「桂大神楽」拝観でした。神楽もさることながら、集落の方、応援の方の「おもてなし」含め、とても素晴らしい神楽でした。
最近では過疎化や高齢化によるほしゃこ(舞手)の減少で、神楽保存の取り組みも難しくなってきているとのことですが・・続けて欲しいものです。
絶やしてはならないという想いから、このようなページを作成、陰ながら応援しております。
令和2年 桂大神楽 演目(当日頂いた資料より一部抜粋)
- 舞入れ(全員) 10:50 神宿よりご祭神、お供の方と共に舞い込む
- 【1】宮神楽(二人舞い) 11:05 宮神楽は、神社の前や鳥居遷宮の際に舞う神楽で、東征の上のじからの立ち舞いと同じである。神前を清める舞いとされる。
- 【2】荒神の言い句(三人舞い) 荒神一方二方、神主 11:30 神主と地主荒神との問答神楽。宮清めとして行われる。桂神楽では新しく宮が建ったり、鳥居建立の折に宮神楽とともに行われる。
- 【3】神おろし(全員) 12:00 八百万の神々をみこうやにお迎えする神楽
- 【4】とうせい(東征)(二人舞い)森のしょうぎょう 12:30 通常、例祭等で最初に舞われる神楽。神楽の入門時に練習することで、他の神楽にも通用してくる。大神楽の時だけ森のしょうぎょうがはいる。
- 【5】杉のぼり(二人舞い) 13:00 桂神楽の中で特徴である「からすとび」が後半にある。早く、激しい舞いになる
- 【6】おだいじん(三人舞い) 1番~11番 13:30 伊勢天正大神のいわれをとくしょうぎょう、及び神楽
- 【7】たぢからさま(二人舞い) 面と舞だし 16:30 太力男命の舞い
- 【8】ぢわり(四人舞い) 1番~13番 17:00 大地の神を敬う舞い。五穀豊穣に感謝する(ちょうし、盃、しらきの豆腐)
- 【9】ゆみのしょうご(二人舞い) 1番~6番 19:30 弓、矢を持って舞う 狩猟の舞いとされる。
- 【10】八幡様(二人舞い) 八幡様の面と舞い出し 20:50 桂正八幡神社の御神体の舞。桂神楽三番として東征、杉のぼりと共に例祭の時に舞われる。
- 大祓 21:30 夜中のみこうや清めが行われる。その後、夜中のぞうすいを食す慣わしがある。観客席にも振舞う。
- 【11】夜中のとうせい(二人舞い) 22:00 みこうや清めとして舞われる
- 【12】しばいれ(全員) 22:20 かまど荒神が榊束にまたがり、みこうやに舞い込む。
- 【13】荒神の言い句(三人舞い) 荒神一方二方、神主 22:30 問答は2、と同じである。日々かまどの火を使うことへの感謝の意がある。古くから地主荒神、かまど荒神は大事にされてきた。
- 【14】かんずい(五人から一人舞い) 1番~7番 23:00 かんずいは桂神楽を代表する舞いといわれ真剣白刃による立ち舞い。ほしゃこはこの神楽が終わるまでみこうやの外に出て身を汚さずと言われている。
- 【15】みかさ神楽(十人舞い) 1:00 女装したほしやこが田植えの舞を行う。
- 【16】稲荷神楽(二人舞い) 1番~7番 1:30 稲荷大明神のしょうぎょうを説く 五穀豊穣の舞であり旧暦初午の日に舞われる
- 【17】ごってんのう(四人舞い) 1番~6番 4:20 山の神の舞
- 【18】おきえ(二人舞い) 4:20 水神(海)の舞
- 【19】歳の神(二人舞い) 5:40 歳徳神(その年の吉方位の神・万事に吉)のしようぎょうを説く 五穀豊穣、子孫繁栄の舞であり目覚まし神楽としてこっけいな舞をする
- 【20】岩戸五番の開き
(一人舞い) しょうぎょう 伊勢神楽 6:00 岩戸神話のいわれをしょうぎょうで説く。
(一人舞い) しばとり 「おぼろ月夜のごとくなりたもその時、ふでんおうはしばを引きこぎ」としようぎょうに唄われるしばとりの舞
(一人舞い) 戸とり 「と隠しの明神なましまして、おくせんざいの力を出し弓手の戸を取り……」とうたわれる戸とりの舞
(一人舞い) とんちく面 うずめの舞とされる
(二人舞い) 大神宮引き出し 6:40 太力男命力が天照皇大神引き出す舞
- 【21】願成就神楽(三人から一人舞い) 1番~6番 7:00 祈願裁就の舞 高天の原より出た二本の綱を二人で持って舞う よじれた網が解けることにより成就を表す 神と人との心をつなぐ
- 【22】神おくり(全員) 8:00 すべての神楽が終わり八百万の神々を元の社に納める舞
参照元:当日頂いた資料(PDF)番付含め全4枚・約2MB パスワードは kagura)
肖像権・プライバシー権について
神楽を舞われている方、神楽関係者以外の観客の方については、肖像権、プライバシー権の観点より、お顔が認識出来ない程度のボカシ加工を行っております。何か問題等ございましたらメールを頂ければ、すぐに対処しますのでご連絡をお願いします。
夜神楽観賞の心得
以下は、諸塚村観光協会サイトより引用諸塚の神楽は、各集落の住民の手で伝承されてきた神聖なお祭りです。山間部の神楽に共通する事ですが、周辺道路は、すれ違い出来ない狭いところも多いです。
そこに参加させてもらうというお気持ちでお越しください。
・夜神楽の会場付近に宿泊施設はございません
・地元では、神事へ参列するお供えとして焼酎(2~3升程度)かそれに相当する御神前を持参する慣わしになっています。
・夜神楽が奉納されるのは、民家や集会場に作られる御神屋(みこや)。基本的に屋外での見学となりますので、防寒対策はしっかりと。
/ 引用おわり
季節柄、雪が降り、日陰などは凍結している場合もあります。
天気予報をチェックの上、雪が降りそうな場合には、チェーン等滑り止めを携帯し、運転には十分注意してください。
The contents of this site are written in Japanese only Please use English translationsite.
【サイト内検索のご案内】
当サイト内には多くの神楽の関連ページ/写真があります。
以下より、当サイト内の検索が出来ます。
画像検索もできますので、写真を探すことも出来ます。
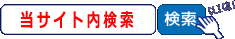
桂大神楽(桂神楽) トップページ 〔諸塚神楽〕
【当サイトブログ】|毎日更新(目標)アラカルトブログ
|Twitter|Facebookページ|
Reproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.
Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.
-PhotoMiyazaki -
Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.
-PhotoMiyazaki -