

尾狩神楽(おがりかぐら)〔宮崎県 西臼杵郡高千穂町 向山尾狩地区〕
尾狩神楽(全5ページリンク)
- 山中神社~舞入れ(このページ)
- 神楽1:【1】彦舞(ひこまい)【2】御小屋の舞(みこやのまい)【3】とうせい【4】鎮守(ちんじゅ)【5】杉登(すぎのぼり)【6】山中様(やまなかさま)
- 神楽2:【7】神降(かみおろし)【8】地固(ぢがため)【9】荒神(こうじん)【10】住吉(すみよし)【11】大神(だいじん)【12】田植神楽(たうえかぐら)【13】杵の舞(きねのまい)【14】箕舞(みまい)
- 神楽3:【15】岩くぐり(いわくぐり)【16】座張り(ざはり)【17】五つ天皇(ごってんのう)【18】八つ鉢(やちばち)【19】武知の舞(ぶちのまい)【20】山森(やまもり)【22】弓正護(ゆみしょうご)【23】沖逢(おきえ)【24】注連口(しめぐち)
- 神楽4:【25】伊勢(いせ)【26】岩戸大力男(いわとたぢからお)【27】鈿女(うずめ)【28】柴引(しばひき)【29】戸取り(ととり)【30】手力雄(たぢからお)【31】日の前(ひのまえ)【32】繰下し(くりおろし)【33】雲下ろし(くもおろし)
~ PhotoMiyazaki宮崎観光写真サイトについて ~
当サイトは、写真中心のサイトです。パソコンの壁紙サイズの写真も多く掲載、出来れば大きな画面でご覧ください。
主な写真は写真上をクリックすると、画面幅サイズに拡大します。拡大した左上のアイコンをクリックするとさらに拡大、マウス操作でシームレスに拡大縮小します。
スマホ等でうまく拡大しない場合には、写真下の文字リンクをタップしてください。
主な写真は写真上をクリックすると、画面幅サイズに拡大します。拡大した左上のアイコンをクリックするとさらに拡大、マウス操作でシームレスに拡大縮小します。
スマホ等でうまく拡大しない場合には、写真下の文字リンクをタップしてください。
【情報追記】
平成30年度(2018年)に夜神楽は途絶え、「日神楽」で8番程を奉納しているとの事です。
撮影日:平成30年1月20日~21日
平成29年度の神楽宿:甲斐勲様宅
山中神社夜神楽祭
保存会名:尾狩神楽保存会
平成29年度(奉納は平成30年1月20日~)の神楽宿(甲斐勲様宅)
(※令和二年現在、夜神楽は行われておりません。最新情報は高千穂町サイトでご確認をお願いします。)
地図:GoogleMap Mapfan Mapion
緯度経度:32度39分2.53秒 131度19分5.53秒(日本測地系)
今回、当方は延岡市側のアクセスでしたので、天翔大橋経由で向かいました。最後の数キロは道幅もぐっと狭くなりすれ違い出来ないところも多くなります。分岐点に、神楽の案内板が出ておりましたので助かりました。見逃すと迷う可能性あり。
車の駐車は、道路沿いの空き地を見つけて駐車。
神楽宿の入り口には、当日、山中神社の旗が立っていると思いますので、それを目印に。
山中神社の地図
➡ Google Map尾狩神楽概要
(宮崎県サイトより一部引用)
向山地区尾狩公民館は、尾峰・狩底という二つの小集落で構成された、世帯数11戸の集落。
鎮守社の「山中神社」のご祭神は、山中坊という修験者が人神として祀られている。
伝えでは、山中坊は隣村の秋元集落から旧正月13日の夜に狩底の観音堂に移り住んだが、やがて重い病気にかかり、心配した4集落の里人が交互に飲食を運び、死水をとって往生させたという。
山伏は「この集落の人々の親切は忘れない。死後、吾を祀ったら、疫病の流行から必ず私が護り、法力をもって末永く村を守るので、観音堂より床を低くして祀るが良い。参拝は観音様をまず拝すること。」と臨終のことばを残したという。
尾狩神楽は黒仁田神楽と同様、日之影町岩井川系の神楽で、暴れ神楽といわれる「座張り」や祇園信仰の「五っ天皇」の番付のほか、平地の農神楽である「田植神楽」が組み込まれている。
夜神楽祭は、古くは旧暦1月13日の縁日とされていたが、現在は新暦の1月第3土曜日に行われている。 夜神楽が奉納される神楽宿は狩底集落4軒の家廻しで、神楽料理賄いのために、各家の台所は土間を残し、昔ながらの竈が設けられている。 神楽伝承者は15名で、氏子数が少ない為、舞手も準備から賄いまでの全てに従事している。
➡ 参照元
関連資料リンク
➡ 尾狩神楽宮崎県教育委員会 文化財課 平成29年(2017年)発行(PDF)
日之影町との境にあり、「座張り」など岩井川神社神楽などと同じ番付があったり、他の集落で舞われる「御神体の舞」がなく、田植神楽、杵の舞、箕舞など、宮崎市・日南市など平野部の春の作祈祷神楽で見かけるような番付があったり、興味深い内容でした。
私の神楽関連の愛読書「宮崎の神楽 祈りの原質・その伝承と継承 / 山口保明著」でも、山中神社神楽の田植神楽、杵の舞、箕舞などについてふれており、おそらくは平地作神楽の番付を取り入れたものでしょう。と記載されておりました。
以下は、当日いただいた番付表より引用
山中神社夜神楽祭
尾狩 乙草 氏子一同
番・名・説明
- 【1】彦舞(ひこまい)猿田彦命の舞 序曲、始楽
- 【2】御小屋の舞(みこやのまい)神を招く神庭をつくる舞
- 【3】とうせい 式三番の二番目の舞
- 【4】鎮守(ちんじゅ)土地を祓い固め荒神を鎮める舞
- 【5】杉登(すぎのぼり)昇神の舞 神を送る
- 【6】山中様(やまなかさま)山中神社(氏神様)の舞
- 【7】神降(かみおろし)降神の舞で神を招く優美な舞
- 【8】地固(ぢがため)剣、即ち水の得で耕地をうるおして国創りをする舞
- 【9】荒神(こうじん)荒神の舞
- 【10】住吉(すみよし)海神の舞
- 【11】大神(だいじん)大わたつみの神(海の幸)の清めの舞、願かけ願ほどきの神楽
- 【12】田植神楽(たうえかぐら)米植えから、刈取りまでの豊作祈願の舞
- 【13】杵の舞(きねのまい)杵(きね)を持って穀物の豊作を祈る舞
- 【14】箕舞(みまい)豊作を感謝し、箕(み)をふるう舞
- 【15】岩くぐり(いわくぐり)剣の舞、自刃を持ち回転などをする勇壮な舞
- 【16】座張り(ざはり)剣の舞にはいる面の舞
- 【17】五つ天皇(ごってんのう)防火の舞
- 【18】八つ鉢(やちばち)少彦名命が太鼓に乗って身軽な舞をする
- 【19】武知の舞(ぶちのまい)むちかむしとも言い山森の前奏曲風難よけの舞
- 【20】山森(やまもり)山の神に祈る舞
- 【21】山神(やまのかみ)山の神としし(猪)の舞 (今年は割愛)
- 【22】弓正護(ゆみしょうご)弓を持ち、弓矢の呪力で悪魔を払う舞
- 【23】沖逢(おきえ)水神を祭る火伏せの神楽
- 【24】注連口(しめぐち)神々をお送りする舞
- 【25】伊勢(いせ)岩戸を探る舞で岩戸開きの舞
- 【26】岩戸大力男(いわとたぢからお)岩戸五番のはじまり 天岩戸を探しあてるところ
- 【27】鈿女(うずめ)うずめの命の舞 天岩戸の前の舞、神楽のはじまり
- 【28】柴引(しばひき)天香久山の柴をを引き砦戸の前に飾る舞
- 【29】戸取り(ととり)天岩戸の戸を開く舞
- 【30】手力雄(たぢからお)天岩戸を開き喜び祝う舞
- 【31】日の前(ひのまえ)天照大神の出御の舞 月よ日よ・・と歌い祝福する
- 【32】繰下し(くりおろし)雲下ろしの用意
- 【33】雲下ろし(くもおろし)雲(内注連)をおろし舞納めの舞
山中神社
当、山中神社の祭神 山中様は、昔から流行(はやり)病・熱病に霊験あらたかな神として知られ、県内外から多数くの参拝を受けています。 旧暦の一月十三日が縁日になりますが、現在は新歴の第三土曜日に秋の実りに感謝し、来る年の豊作と家内安全、無病息災、氏子の繁栄を祈願して神楽を奉納しています。 / 引用終わり
山中様
山中様として祭祀されている石像は、高さ90cm、右手に錫杖、左手に法螺貝を持った山伏像で、台座に1843年(天保14年)卯八月と刻してあるとのこと。




山中神社横にある、建物で式三番が奉納される。(16:00頃)






神社での神事の後、「綾」と呼ばれる白布で神の道を祓い浄め、猿田彦、山中様を本殿から導きだす「綾祓い」がお紺われる。
綾で頭を撫でられると健康に過ごせると云う。
山中神社から神楽宿へ向かう前に神社を3周する(17:40頃)


写真で見るとそうでもないですが、この頃になると、結構暗くなっており、シャッタースピードは1/15秒程(F4・ISO3200)、そのまま撮ってもブレるので、流し撮りで。












神楽宿へ舞入れ(18:00頃)


















肖像権・プライバシー権について
肖像権・プライバシー権の観点より、見学者の方については、お顔が認識できない程度にボカシ加工を加えております。文言等含め、間違い、不都合などございましたらメールをお願いします。
以下は高千穂町、高千穂の夜神楽案内より一部引用
夜神楽の「ふるまい」について
- 夜神楽は秋の収穫感謝、冬の鎮魂儀礼、春の豊穣余祝を祈願する「氏神様の村まつり」です。高千穂の村まつりは、氏神様を里の神楽宿にお招きし、33番の神楽を夜を徹して奉納するのが、古くからのシキタリです。祭り風景のなかで、カッポ酒、煮物料理等のふるまいが紹介されていますが、「ふるまい」は、年に一度降臨された神々と里人が神人一体となる直会の儀式料理です。
- 近年、本物志向から「村まつり」に参座される観光客の方々も年々増加し、交流として「ふるまい」をされる集落も増えていますが、その接待は神事儀礼の一環であり、村々の考えで行われています。
- お見えになった方々が、食事代として、初穂料・ご神前を供えられ、ふるまい料理を要求される事も多々ありますが、村各々のシキタリの中で接待されますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
尾狩神楽(全5ページリンク)
- 山中神社~舞入れ(このページ)
- 神楽1:【1】彦舞(ひこまい)【2】御小屋の舞(みこやのまい)【3】とうせい【4】鎮守(ちんじゅ)【5】杉登(すぎのぼり)【6】山中様(やまなかさま)
- 神楽2:【7】神降(かみおろし)【8】地固(ぢがため)【9】荒神(こうじん)【10】住吉(すみよし)【11】大神(だいじん)【12】田植神楽(たうえかぐら)【13】杵の舞(きねのまい)【14】箕舞(みまい)
- 神楽3:【15】岩くぐり(いわくぐり)【16】座張り(ざはり)【17】五つ天皇(ごってんのう)【18】八つ鉢(やちばち)【19】武知の舞(ぶちのまい)【20】山森(やまもり)【22】弓正護(ゆみしょうご)【23】沖逢(おきえ)【24】注連口(しめぐち)
- 神楽4:【25】伊勢(いせ)【26】岩戸大力男(いわとたぢからお)【27】鈿女(うずめ)【28】柴引(しばひき)【29】戸取り(ととり)【30】手力雄(たぢからお)【31】日の前(ひのまえ)【32】繰下し(くりおろし)【33】雲下ろし(くもおろし)
The contents of this site are written in Japanese only Please use English translationsite. 【サイト内検索のご案内】
当サイト内には多くの神楽の関連ページ/写真があります。
以下より、当サイト内の検索が出来ます。
画像検索もできますので、写真を探すことも出来ます。
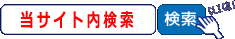
高千穂の夜神楽 尾狩神楽〔宮崎県 高千穂町 向山尾狩〕
Reproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.
Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.
-PhotoMiyazaki -
Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.
-PhotoMiyazaki -