九州の神楽シンポジウム2020 1/5 遠山の霜月祭(湯立・四面)
- 【1Page】遠山の霜月祭(湯立・四面)現在ご覧のページ
- 【2Page】遠山の霜月祭(八社の神・襷の舞・冨士天伯)
- 【3Page】中之又神楽(獅子舞・獅子とり荒神)
- 【4Page】桂神楽(荒神の言い句〔問答神楽〕)
- 【5Page】桂神楽(みかさ神楽)
令和2年(2020年)1月18日(土)、19日(日)、宮崎市 メディキット県民文化センター 演劇ホール で13:00より、「九州の神楽シンポジウム2020」が開催されました。
撮影OKという事でしたので、カメラ持参、関係者の方々の記念になればと思い、神楽の写真を主に5ページにわたり掲載しました。
神楽の説明文は、主に当日頂いたプログラムより転載しました。(転載部分は色変更)
➡ 当日頂いたプログラム紹介ページ
1日目 1月18日(土) 13:00開演
神楽公演
上五島神楽(上五島神楽保存会、長崎県新上五島町)シンポジウム
テーマ:「神楽と豊穣祈願」基調講演
「稲作、狩猟の祈願・祈としての神楽」講師:松尾 恒一氏(国立歴史民俗博物館教授)
パネルディカッション
コーディネーター : 小川 直之氏(國學院大學教授)パネリスト:
段上 達雄氏(別府大学教授)
安田 宗生氏(熊本大学名誉教授)
立平 進 氏(長崎県文化財保護審議会副会長)
前田 博仁氏(宮崎民俗学会会長)
櫻井 弘人氏(飯田市美術博物館専門研究員)
2日目 1月19日(日) 13:00開演
基調講演
「日向神楽の伝承土壌」講師:野本 寛一氏(近畿大学名誉教授)
神楽公演
遠山の霜月祭 (上村遠山霜月祭保存会、長野県飯田市)中之又神楽(宮崎県木城町)
桂神楽 (宮崎県諸塚村)
河野知事挨拶


− 河野知事挨拶 −
基調講演
「日向神楽の伝承土壌」講師:野本 寛一氏(近畿大学名誉教授)


− 野本 寛一氏 −
遠山の霜月祭(上村遠山霜月祭保存会、長野県飯田市)
長野県飯田市遠山郷の各集落で伝承されており、毎年12月(旧暦の霜月)に行われる霜月神楽であり、新たな一年の息災を願う祭りである。この祭りの起こりは地元の伝承では平安時代の終わりとも鎌倉時代ともいわれている。後に、徳川幕府に改易された遠山氏一族を「八社の神」として合祀している。社殿内に土製の竃(かまど)を設けて湯釜2口を据え、その周りで神事や湯立、さまざまな舞を行う。15立くり返される湯立のあと、夜明け近くに17の面(おもて)が登場する。昭和54年国重要無形民俗文化財指定。関連サイト(外部)
➡ 遠山の霜月祭り 信州遠山観光協会公式サイト(外部リンク)
この日は、飯田市上村上町地区の保存団体の会員ら16人が神楽を披露した。


− 遠山の霜月祭(湯の上飾り) −
遠山の霜月祭 湯立(ゆだて)
祭りの中心となる演目。湯立ては本祭り約18時間のうちの10時間、延々と繰り返される。遠山の霜月祭は複数の神事を同時進行するという特徴があったが、今では今日出演する地区(上村上町の正八幡宮)だけとなっている。湯立の途中に「大宮清め」という祭りの場所すべてを清める神事と、「上げ湯」という神々に湯を献ずる神事を同時に行う。


− 遠山の霜月祭(湯立) −


− 遠山の霜月祭(湯立) −


− 遠山の霜月祭(湯立) −


− 遠山の霜月祭(湯立) −


− 遠山の霜月祭(湯立) −
遠山の霜月祭 四面(よおもて)
水、土、火、木の神をかたどった四つの面を「四面」と呼ぶ。水と土の神が登場し、煮えたぎった釜の湯を素手で跳ね飛ばし、氏子に浴びせる。湯をはねた後は、氏子に噺立てられて、氏子の中へ飛び込んでいく。(今回は、時間の関係で、「水王(みずのおう)」「土王(つちのおう)」だけ登場、会場では水や火が使えない為「水王」「土王」の面を被って釜の中で沸騰した湯を素手ではじく「湯切り」は、加湿器の蒸気で湯気を表現していた。)


− 遠山の霜月祭(四面) −


− 遠山の霜月祭(四面) −


− 遠山の霜月祭(四面) −


− 遠山の霜月祭(四面) −


− 遠山の霜月祭(四面)土王 −


− 遠山の霜月祭(四面)水王 −


− 遠山の霜月祭(四面) −
- 【1Page】遠山の霜月祭(湯立・四面)現在ご覧のページ>
- 【2Page】遠山の霜月祭(八社の神・襷の舞・冨士天伯)
- 【3Page】中之又神楽(獅子舞・獅子とり荒神)
- 【4Page】桂神楽(荒神の言い句〔問答神楽〕)
- 【5Page】桂神楽(みかさ神楽)
The contents of this site are written in Japanese only Please use English translationsite. 【サイト内検索のご案内】
当サイト内には多くの神楽の関連ページ/写真があります。
以下より、当サイト内の検索が出来ます。
画像検索もできますので、写真を探すことも出来ます。
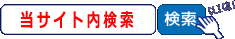
九州の神楽シンポジウム2020 1/5 遠山の霜月祭(湯立・四面)
Reproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.
Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.
-PhotoMiyazaki -
Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.
-PhotoMiyazaki -