

 文化審議会は2026年1月23日「高鍋神楽」を国重要無形民俗文化財に新たに指定するよう、文部科学相に答申しました。 ➡ 当ブログ記事にも記載
文化審議会は2026年1月23日「高鍋神楽」を国重要無形民俗文化財に新たに指定するよう、文部科学相に答申しました。 ➡ 当ブログ記事にも記載令和7年「六社連合大神事」
日時:12月6日~7日7:00 比木神社(木城町)
旧高鍋藩の比木神社(木城町)、八坂神社、愛宕神社(高鍋町)、自髭神社、平田神社(川南町) 八幡神社(新富町)が輪番で開いている行事。
令和7年は比木神楽の番ですので、毎年奉納されている比木神楽が充当する。
比木神楽(高鍋神楽) 1/8Page (トップページ)
- 1Page:比木神楽 トップページ
- 2Page:1 壱番神楽、2 花の手
- 3Page:3 大神、4 鬼神、5 将軍、6 振揚、7 かんなぎ
- 4Page:8 荒神、9 伊勢舞、10 手力雄、11 伊勢神楽
- 5Page:12 神師、13 大神神楽(神武神楽)
- 6Page:14 闢開神楽、15 闢開鬼神、16 将軍、17 寿の舞、18 舞揚
- 7Page:19 手力、20 戸開雄(動画あり)
- 8Page:21 繰卸、22 神送神楽 / その他
比木神社
御祭神:大己貴命(おおなむちのみこと、大国様)
お妃 三穂津姫命
事代主命(恵比寿様)
スサノヲノミコト、お妃 櫛稲田姫命
福智王(ふくちおう)
比木神社は今から1800年前「第13代成務天皇の御代 武内宿禰(たけしうちのすくね)に命じ国、県(あがた)、邑(むら)、里(さと)を定められた時、社領として100町歩を賜り五社大明神を崇め奉祀ったのが始まりと伝えられ極めて古い創建の神社であります。
以来、児湯地域の信仰の中心として住民の篤い崇敬を集め、幾星霜(いくせいそう)、特に江戸時代には、高鍋藩 秋月歴代藩主深く崇められ度々参拝し、社殿改築、鳥居の建立、龍神絵など多く寄進奉納されています。




比木神社 アクセス・地図等の情報
鎮座地:〒884-0102 宮崎県児湯郡木城町大字椎木1306番地イ地図:GoogleMap Mapfan Mapion
緯度経度:32度9分42.55秒 131度27分10.65秒(日本測地系)
比木神社の夜神楽(神事)
比木神社で神楽が奉納されるこのお祭りは「神事(かみごと・かみごつ)」と言われております。高鍋神楽の中心的役割を担っている比木神楽が文献上に現れたのは、寛永20年(1642)のことです。
その当時、秋月氏が東児湯地区一帯を治めていました。
「高鍋藩本藩実録」によれば、秋月氏は徳川家康に関ケ原の戟いでの功績を認められ、日向の国に所領を安堵されて間もなく、お姫様が病の床に伏されました。医師が手立てを尽くすも、なかなか回復の兆しが見えなかったことから領内にお達しを出されました。高鍋の上江鴫野の住人・大寺余惣衛門という者が申し出て、比木神社へ心を込めて日参したところ、不思議なことにお姫様の病は次第に快方に向かい、遂には全快されたのです。
お殿様は大変喜ばれて、比木神社にお礼の参拝をされ、終夜神楽を奉納して神恩感謝の誠を捧げられたのです。
それ以来、比木神社では12月5日(現在は12月の第一土曜日)に夜を徹して神楽を奉納する「神事」が行われるようになったのです。(「宮崎の神楽と特殊神事/宮崎県神社庁)
※「高鍋神楽」は、宮崎県児湯郡の都農町、川南町、高鍋町、木城町、新富町の東児湯5町の神社で奉納される(都農神楽、比木神楽、三納代神楽)の総称で、県指定無形民俗文化財に指定されている。
昭和53年1月31日には国の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」にも登録されている。
高鍋神楽 保存会の内訳
- 高鍋町 高鍋神楽 高鍋神楽 高鍋神楽保存会 国選択「高鍋神楽」
- 木城町 高鍋神楽 比木神楽 比木神社 国選択「高鍋神楽」
- 新富町 高鍋神楽 三納代神楽 三納代神楽保存会
- 都農町 高鍋神楽 都農神楽 都農神楽保存会 国選択「高鍋神楽」
- 美郷町 高鍋神楽 神門神楽 神門神社伶人会
比木神楽 神事
神楽奉納に先立ち、修祓、降神、献僕、祝詞奏上など神事が行われる。








山(神籬)
山(神籬)の建て方大神事(大々神楽)を執行するため、神社の境内の清浄な所に神楽域を設定する。その奥まった東北の地より南西に最も高いところ8m、低い所2m位の三角形の山を、樫か惟木をを用いてすき間のないように立てる。
それに13本の大幣(高幣)を立てる(別図のように)特に中心の人幣を起す場合は笛太鼓の奏楽の裡に立てる。
玄の幣9本、闢開(赤・白布各一匹)は憐に張る。其処から、四方に八ツ注連縄を張り、その縄に幣と笠もしくは扇を八つつける。神楽場の四方角には注連竹を立て注連縄を張り四つの幣を下げる。
山(神雛)の前下に長さ四間奥行三尺の神座をを設け、中央に台座をしつらえ、その前に八つの御幣を取りつける。
その上に繰りかけを取りつける。その上に繰り下ろし円〆ををとりつけ、それに幣三十三本を立てる。東西南北の四角と寅卯(中央の分をこの寅卯に立てる)の〆竹に、神の璽(じ)の御幣を結びつける。
高鍋神楽 昭和54年度 高鍋神楽保存会 より引用
※近年、骨組みについては竹の代わりに鉄パイプを代用しているようです。




神楽が始まるのを待つ人々


極寒の中、炭火がありがたい
12月初旬、かなり冷え込みます。翌朝の気温はマイナスでした


参考資料:比木神楽 番付
参照元:下段記載「宮崎の神楽と特殊神事/宮崎県神社庁」
- 御神楽: 一番神楽とも称し基本の神楽である
- 花の手: 二人舞で地清め
- 荒神返し: 現在行われていない
- 大神舞:面を被り一人舞
- 敏伐舞:二人舞で地固め
- 鬼神舞:鬼神面を被り鬼神杖と扇子を持って一人舞
- 将軍舞:二人舞で、弓矢を持って舞う
- 間舞:九番の節と問答の後一人舞
- 節舞:荒神面をつけ一人舞
- 舞揚:神職が一人で舞う
- 磐石:「めごんめ」と呼ばれ赤衣を若し御幣、杓子、すりこぎ、椀を持って舞う
- 神師舞:本手は8?12人で剣と鈴を持って舞う
- 振揚舞:抜身の太刀を持って舞う 一人舞
- 地割:現在舞われていない
- 帳読:奉納者名の読み上げ
- 祝詞:奉納者祈願奏上
- 闢開神楽:二人舞で、鈴と扇子で舞う
- 闢開鬼神:御幣付きの杖と扇子で一人舞
- 繰掛卸舞:本手は8?12人で神楽を舞い、次に綱と鈴、次に綱のみ
- 御笠神楽:鈴と扇子で宮神楽 二人舞
- 笠取鬼神:六番神楽と同じで、笠のみを持って舞う
- 御笠神酒上:一人舞で神楽の縁起を唱え神酒を捧ぐ
- 御笠将軍:現在舞われていない
- 御笠練舞:多人数で御幣を持って舞う。「田植舞」とも呼ばれ氏子も舞う
- 獅子舞:雌雄二匹の獅子が荒れ廻り二十六番の鬼神に捕らえられる舞
- 綱取鬼神舞:一人舞。舞が終わった後、雌雄の獅子を取り鎮める
- 寿の舞:翁の舞で腰を折っての一人舞
- 伊勢舞:一人舞で御幣、鈴、扇子を持ち、最後に神楽縁起を唱う
- 手力雄舞:一人舞。手力面を被り御幣二本と鈴を持って舞う
- 戸開雄舞:一人舞。戸開き面を被り舞う 天の岩戸開きの舞
- 大神:面を被り天冠を戴き両手に日月と岩戸を持って座す
- 繰卸舞:本手は8?12人で鈴、綱などで舞う
- 神送り神楽:御笠神楽の略の舞
上記が、本来の比木神楽の神楽番付ですが、令和元年は、比木神楽の他に、三納代神楽、他の加勢も加わった番付構成となっています。
令和元年 比木神楽番付
| 番 | 舞 | 人数 | 面 | (分) | 担当(注1) |
| 1 | 壱番神楽 | 2 | 30 | G | |
| 2 | 花の手 | 2 | 34 | H | |
| 3 | 大神 | 1 | 〇 | 11 | H |
| 4 | 鬼神 | 3 | 〇 | 26 | H |
| 5 | 将軍 | 2 | 18 | M | |
| 6 | 振揚 | 1 | 16 | H | |
| 7 | かんなぎ | 1 | 24 | M | |
| 8 | 荒神 | 1 | 〇 | 19 | M |
| 9 | 伊勢舞 | 1 | 29 | H | |
| 10 | 手力雄 | 1 | 〇 | 21 | M |
| 11 | 伊勢神楽 | 1 | 19 | M | |
| 12 | 神師 | 6 | 25 | H・G | |
| 13 | 大神神楽(神武神楽) | 5 | 〇 | 44 | M |
| 14 | 闢開神楽 | 2 | 13 | H | |
| 15 | 闢開鬼神 | 1 | 〇 | 29 | G |
| 16 | 将軍 | 2 | 24 | H | |
| 17 | 寿の舞 | 1 | 〇 | 26 | H |
| 18 | 舞揚 | 1 | 12 | G | |
| 19 | 手力 | 1 | 〇 | 20 | G |
| 20 | 戸開舞 | 1 | 〇 | 14 | H |
| 21 | 繰卸 | 8 | 21 | H・G | |
| 22 | 神送神楽 | 2 | 2 | H |
〔H〕比木神楽
〔M〕三納代神楽(新富町三納代八幡宮)
〔G〕グループ高鍋神楽
「グループ高鍋神楽」の説明については、下段で紹介しております「比木神楽 百済王族祭祀と高鍋神楽の広がり / 前田博仁著」より一部引用させていただきます。
「高鍋神楽」と称する神楽保存団体が存在する。呼称は当ページでも準じました。
高鍋二人、川南一人、神門一人(日向市在住)の四人で構成する伶人・舞手集団、これらの人々は高鍋神楽会会員でもある。
通常、県内の神楽保存団体は地区の鎮守や地域に所属することがほとんどで、近年継承者不足から保存会を結成することがあるが、「高鍋神楽」の人たちは高鍋八坂神社や愛宕神社に所属せず、比木神社や三納代の八幡神社などの伶人、舞手の人たちとは有り様が異なる。
「高鍋神楽」は六社連合大神事では欠かせない集団で、演舞も洗練され高い評価を得ている。
高鍋神楽会には比木神社の神職や伶人をはじめ六社連合の神楽関係者も会員であり、その点では同じと言える。ただ、高鍋神楽という語桑は高鍋町内をはじめ東児湯では馴染まれ、県内でも高鍋神楽は広く知れ渡っていることから、「高鍋神楽」と称する保存団体を「高鍋神楽」で述べると混乱を生じる恐れがある。そのことをふまえて、本冊子では便宜的に「グループ高鍋神楽(G高鍋神楽)」と仮称して述べる。
令和元年 比木神楽の写真
以下では、各番付1枚のみを掲載、リンク先には多くの写真があります。日向高鍋神楽の由来
高鍋神楽の起りといはれる、現在木城町比木(古くは比企)に鎮座の比木神社の「御里廻り」の神事は古く、その「おみゆき」の如きは東臼杵都南郷町神門神社迄往十日間を要する大業なものにて、その禅門神社の境内の神木にその昔、神楽奉納の砌射込まれたと思はるる鏃(やじり)が出現、それは鎌倉時代以前に射込まれたものであると云はれる。(昭和54年度、高鍋神楽保存会発行「高鍋神楽」より)師走祭り
百済王の亡命 親子の一年に一度の再開 師走祭り師走祭りは 西暦660年、朝鮮半島の百済が、唐と新羅の連合軍に攻め滅ぼされ、663年百済再興の戦いにも破れ、多くの王族、部族は日本の畿内へと亡命した。
その後、7世紀から8世紀中に日本に頻発した政治事件によってこの地、現在の美郷町と木城町に百済の王族が亡命した、という伝説を基に構成された祭りです。
百済の王族であった父親の禎嘉王(ていかおう)は現在の日向市の金ヶ浜に漂着、その後、美郷町南郷区神門へ、息子の福智王(ふくちおう)は現在の高鍋町の蚊口浦に漂着、その後、木城町に住み、亡くなったのち、それぞれが神として美郷町の神門神社に、木城町の比木神社に祀られました。
師走祭りは木城町の比木神社に祭られている王子・福智王のご神体が、父・禎嘉王を祭る美郷町の神門神社まで年に一度巡行面会に来るというものです。


福智王の御神体(袋神)を奉じる比木神社の御神幸が続く






「師走祭り」は別途WebPageを作成しています。
➡ 師走まつり
六社連合大神事
秋月氏が高鍋の地を領するや累代藩主内に鎮座する六つの郷社を特に尊崇、その六社を輪番にて年に一度の大神事を行事と定め、国家安泰、息災延命、武運長久、家中安全、諸人息災延命を祈願して、幣(御神楽料)を奉献、大々 神楽三十三番を斉行した。現在も 旧高鍋藩内の 白鬚神社(川南町白鬚)・平田(へいた)神社(川南町平田)・八坂神社(高鍋町高鍋)・愛宕神社(高鍋町上江)・比木神社(木城町椎木)・八幡神社(新富町三納代) 輪番にて例年旧暦十二月二日宵から、翌三日夜明にかけて神楽三十三番が執り行われている。(※白髭神社は現在途絶えているようです。)
最近は、宮司や氏子を含めた、高鍋神楽保存会の合議により、旧奉納日に近い土日に設定されることが多い。
比木神社が輪番となった年度は「比木神楽」を兼ねる。
➡ 平成29年 六社連合大神事 リーフレット


参考資料:昭和54年度 高鍋神楽保存会(PDF)(都農神楽保存会サイト内) 当サイトは、写真メインのサイトです。拡大写真はフルハイビジョン幅(1920pix)です。出来ればパソコン等の大きな画面でご覧ください。
主な写真は写真上をクリックすると、画面幅サイズに拡大します。拡大した画面の左上にるアイコンをクリックするとさらに拡大、マウスの回転操作でもシームレスに拡大縮小します。
スマホ等、モバイル端末などでうまく拡大しない場合には、写真下の文字リンクをタップしてください。
比木神楽(高鍋神楽) 以外の宮崎県内で撮影した神楽の写真も、数多く掲載しております。以下をご覧ください。
➡ 宮崎県の神楽
肖像権・プライバシー権について
神楽を舞われている方、神楽関係者以外の観客の方については、肖像権、プライバシー権の観点より、お顔が認識出来ない程度のボカシ加工を行っております。何か問題等ございましたらメールを頂ければ、すぐに対処しますのでご連絡をお願いします。
- 1Page:比木神楽 トップページ
- 2Page:1 壱番神楽、2 花の手
- 3Page:3 大神、4 鬼神、5 将軍、6 振揚、7 かんなぎ
- 4Page:8 荒神、9 伊勢舞、10 手力雄、11 伊勢神楽
- 5Page:12 神師、13 大神神楽(神武神楽)
- 6Page:14 闢開神楽、15 闢開鬼神、16 将軍、17 寿の舞、18 舞揚
- 7Page:19 手力、20 戸開雄(動画あり)
- 8Page:21 繰卸、22 神送神楽 / その他
当方が考える「夜神楽見学上の留意・マナーなど」
一夜の氏子として参加させていただくというスタンスで
宮崎県内各地で奉納されている神楽は、「見世物」ではありません、地域の「祭り」「奉納」です。一夜の氏子として参加させていただくという減り下りスタンスでおねがいします。初穂料の奉納
夜神楽は、供物を持参、奉納します。通常、神楽が奉納されるところ(神社など)には「受付」があるので、焼酎2升(奉納)、または現金3,000円 - 程を「初穂料」として包んだものを奉納します。
焼酎などは地域で好まれる銘柄などありますので、「初穂料」の方が無難では?と、私は思います。
これは、神社でのお賽銭と同じ意味合い+奉仕者(神楽を舞う方)へや関係者への感謝の気持ちであり、「ふるまい」の食事代やお酒の対価ではありません。
車で行かれる場合
比木神社は街からも近く問題ありませんが、山間部集落の夜神楽は、道中、道幅が大変狭く、対向車が来た場合、延々バックしないとすれ違い出来ないところもあります。街灯などはもちろんのこと、ガードレールも無いところも多いです。場所によっては、カーナビに道が出ないところもあります。道を尋ね様にも人家が見つからないケースも多々あります。出来れば、明るい内に現地入りして、帰りも夜が明けてからの移動をおすすめします。
12月、1月、2月の夜神楽は、朝、車の窓ガラスに霜がべったり付いていることがありますので、フロントガラスを覆うようなシートをかけて置くと良いです。また、霜落としのスクレーパーや霜取りスプレーを車に積んでおくと安心です。 1月、2月、山間部では、たまに雪が積もることもあります。事前に天気予報のチェック、タイヤチェーンなど滑り止めの準備を。
夕食・夜食・アルコール類など
山間部の神楽宿(神楽の奉納場所)近くにコンビニなどはまずありません。ご自身の夜食(手軽に食べられる、おにぎりなど)・飲み物などは事前に購入持参しておいた方が無難です。夜神楽見学は自己完結が基本です。アルコール(宮崎は焼酎がメインです。)が振舞われることもあると思いますが、お車の方は、帰りの時間を逆算して酒気帯び運転にならぬよう適度に抑制を(^^;)
防寒には万全に
12月 - 2月の夜神楽は、とにかく寒いです。 ダウンウエア+防寒インナーなど暖かい服装で、ネッウォーマー、帽子、貼るホッカイロ装備、足元から冷えるので、靴下に貼るホッカイロも忘れずに。高千穂など室内で行われる夜神楽でも、窓を開けっ放しのところが主です。寒いです。米良系の神楽や高原の神舞などの多くは「空の下」で奉納されています。ムシロの上に靴を脱いで上がる場合もあります。靴下は二重に履き、柔らかい素材の上履きみたいなものを持参しておくと良いです。座布団(クッション)、ひざ掛け毛布などもあると随分違います。
外の神楽の場合現地にイス・敷物等が用意してある場合もありますが、無い場合でも臨機応変に対応出来るよう、折りたたみの小さ目のイスなどを車に積んでおくと良いです。
外で奉納される夜神楽では、焚火で暖をとるところも多いです。風で火の粉が飛んで来てダウンウエアなどに穴が開く場合もありますので要注意・・経験談(^^;)。
見学場所について
保存会や、関係者の座る場所が決まっていたり、神輿入れ、舞い込み、神事、柴入れなどの際、邪魔になるところなどがあります。早めに行って見学場所を確保される場合、ここで見学しても支障無いか、保存会の方に確認した方が良いと思います。写真・動画などの撮影について
- 神庭には立ち入らない
神楽が舞われる神庭内には、絶対立ち入らないこと、撮影の際、神庭内にカメラ・レンズなども入れない事。 - フラッシュ(ストロボ/スピードライト)
2017年4月に発刊された、みやざきの神楽ガイド / みやざきの神楽魅力発信委員会編 / 鉱脈社(下段で紹介)という本の中の、神楽見学のマナー項目、「カメラ・ビデオの撮影」の項目で、ストロボ(フラッシュ・スピードライト撮影)について、高千穂町文化財保存調査員、中央公民館長 田尻 隆介氏は、"神事芸能であり、ストロボ撮影は舞に支障をきたすこともあるので、控えるべきであろう。"とコメントされておりました。
以前宮崎市で開催された、「みやざきの神楽シンポジュム」でも、フラッシュが伝統芸能鑑賞に及ぼす影響について、とり上げられたことがあります。
- 三脚
県内の神楽では三脚の使用を禁止しているところもあります。
三脚はフラッシュ同様、神楽見学者にとって迷惑なものです。特に制限なくとも、使用するなら他の見学者の頭の高さ以下で、席を離れる際、使用しない時には縮めておくなど、他の方への気配り目配りを。 - 神事の最中は、無暗にシャッターを切らない。
厳粛、静かな中でのシャッター音は結構耳障りなものです。
写真とは関係ありませんが、お祓いの最中は、帽子などをとるよう心掛けたいものです。 - 写り込んだ一般観客の肖像権・プライバシー権に配慮を
写真内に観客の方が写り込んでいる場合、SNSなどに掲載する際には、お顔が認識できない程度の画像サイズにするか、ボカシをいれた方が無難かと思います。 - 灰かぶり、餅とり粉かぶりに注意
暖の焚火の灰や、はだかの餅巻き(最近はビニールに入った餅をまくところが主流ですが・・)は、機材の防塵にご注意を(経験談)
The contents of this site are written in Japanese only Please use English translationsite. 【サイト内検索のご案内】
当サイト内には多くの神楽の関連ページ/写真があります。
以下より、当サイト内の検索が出来ます。
画像検索もできますので、写真を探すことも出来ます。
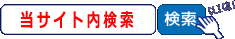
比木神楽(高鍋神楽) 1/8Page (トップページ)
Reproduction or appropriation of HTML, images and photographs from within this site is prohibited.
Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.
-PhotoMiyazaki -
Copyright © MORIMORI All Rights Reserved.
-PhotoMiyazaki -

























